〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町2-26-501
労務三大トラブルの原因
ある日突然、社長が「会社の業績不振によりリストラを実施する。その方針に基づき従業員数名を
解雇する」 と発表したとします。その時、解雇通告を受けた従業員は、果たして納得できるで
しょうか。
リストラとは会社の事業を再構築することです。
そして上記のような整理解雇は、リストラ策の一環として実施されるものです。
しかし、リストラは、その手段や手順を誤ると、事業を再構築するどころか従業員の士気を低下
させてしまいます。
その結果、さらなる業績低迷に陥り、会社の倒産に至るケースさえあります。
では、リストラを実施しても従業員の士気を低下させずにすむ方法はあるのでしょうか?
例えば、Aのようなリストラを実施すれば、従業員はまず納得しないでしょう。
<A>
・他のリストラ手段をとらずに突然、実施される整理解雇
・なぜ自分が整理解雇されるのか、理由が不明確なリストラ
・将来に対する展望が不明確なまま実施されるリストラ
・何回も実施されるリストラ
・「明日はわが身が整理解雇」 と従業員に思わせるリストラ
一方、Bのようなリストラであれば、従業員の士気をそれほど低下させずにすむかもしれません。
<B>
・将来の展望を示し、従業員に希望と目的を与えるリストラ
・整理解雇回避の努力を十分に行ったリストラ
・整理解雇対象者の解雇理由が納得できるリストラ
・リストラの実施による業績の向上
リストラは正しい手段と手順に従って実施し、従業員が納得できるものであるべきです。
特に、整理解雇をする場合、一歩誤ると、泥沼の訴訟紛争に発展しかねません。
整理解雇を伴うリストラの実施に当たっては、事前に次のような要件を検討しておく必要があります。
・不況、経営不振などの理由により、人員を削減することが必要か
―人員削減の必要性
・人員削減をするにしても、整理解雇という手段を選ばなければならないのか
―解雇選択の必要性
・整理解雇対象者の解雇理由は納得のできるものか
―被解雇者選定の合理性
・整理解雇を実施する場合、労働組合または従業員に対して解雇の必要性とその時期、規模、
方法につき納得を得るための説明を行い、さらにそれらの者と誠意をもって協議を行ったか
―手続きの妥当性
整理解雇に係る裁判の判例においても、整理解雇ができる条件として、上の4つの要素を挙げて
います。
ただし、これは4つの要素すべてを充足しなければ整理解雇が有効にならないということではなく、
整理解雇が有効かどうかを判断する際の考慮要素を類型化してまとめたものに過ぎないとしています。
以下では、4つの要素について、それぞれ判断のポイントをみていきます。
□人員削減の必要性
「経営不振により、人員削減をしなければならないのか。それとも人員削減をしなくても不採算
部門の撤退や新たな事業への参入により、経営危機を回避することができるのか―」
従業員の士気を高め会社に活力を与えるためには、不必要な人員削減は避けなければなりません。
では、どのような判断基準に基づき、人員削減が必要か否かを判断するのでしょうか。
企業は資金繰りに行き詰れば事業を続けていくことはできません。
通常、経営不振の会社は銀行などの金融機関から、少なからず借り入れをしています。
従って、人員削減を検討するに当たって、借入金の返済を考慮に入れたうえで、資金繰りに問題が
生じないかどうかを検討することが重要です。
その判断を行うためには、企業の損益状況をシミュレーションしなければなりません。
ここに年商20億円、銀行からの借入金が長短あわせて10億円、年間の借入金返済額が1億円の会社が
あるとします。
「今期見込み」では、この会社は営業利益を1000万円計上する見込みです。
しかし、借入金が多く、支払利息だけでも年間2200万円を支払っており、さらに、年間借入金
返済額1億円を返済すると7700万円ものキャッシュフローの不足が生じてしまいます。
これでは、いくら一生懸命働いても会社にお金が残りません。
この会社の改善策として、人員削減することなく現状と変わらない販売管理費でキャッシュフローが
マイナスにならないようにするためには、「来期対策1」 のような計画が必要になります。
売り上げを23億8500万円、粗利益を2ポイントアップの5億2470万円に設定し、経常利益を1億1770
万円計上しなければなりません。
新規事業を開始してその効果がすぐに表れれば、この数字も不可能ではありませんが、業績不振に
苦しむ会社が、いきなりこうした離れ業を演じるのは、容易なことではありません。
キャッシュフローをいくらに設定して、事業の再構築を図るかが問題です。
例えば、借入金を1億円返済しキャッシュフローで5000万円のマイナスが生じるケースを考えて
みましょう。
「来期対策2」 は、人員削減することなく、現状と変わらない売り上げと販売管理費で事業の
再構築を実施するケースです。
改善策として、粗利益率を2ポイントアップの4億4000万円にしなければなりません。
そのためには、商品構成や仕入れを見直し、粗利益率を22%に引き上げる必要があります。
これが実行されれば、経常利益は3300万円になり、キャッシュフローを5000万円のマイナスに抑え
られます。
一方、 「来期対策3」 では、売り上げは現状維持の20億円、粗利益率は現実的な判断で1ポイント
アップの4億2000万円に設定しています。
しかし、粗利益率を「来期対策2」 より1ポイント低めに設定している分、キャッシュフローを
5000万円のマイナスに抑えるためには、販売管理費をさらに圧縮しなければなりません。
そのため「来期対策3」 では、人員削減を断行する必要に迫られます。
具体的な販売管理費の削減内容は、人員2名削減で1000万円、人件費・減価償却費以外のその他の
販売管理費削減で1000万円、トータルで2000万円となります。
さて、リストラ対策として、来期対策「2」 と「3」 のいずれを選択すればよいのでしょうか。
例えば、手元の現預金が豊富にあり、当面、金融機関からの融資に頼らなくても資金繰りに問題が
なければ、人員削減を断行しないことも可能でしょう。
しかし、手元の現預金が乏しく、金融機関からの資金調達を受けなければ資金ショートを起こす
可能性がある場合には、金融機関との折衝で5000万円のキャッシュフローのマイナスを認めて
もらったうえで、人員削減を実行しなければなりません。
「人員削減の必要性」 について、これまで判例では、 「人員削減を行わなければ企業の維持・存続が
危ぶまれる程度に差し迫った必要性があること」 まで要求する例も少なくありませんでした。
しかし、最近では経営悪化とか倒産の危機などの事態に陥っていなくとも、資本効率を高め、競争力
を維持・強化するという戦略的リストラの目的で行う人員削減まで有効とする判例がみられ、判断
基準が緩和されつつあります。
会社の傷が大きくなった段階で、人員削減を伴うリストラを断行しても、業績は再び低下してしまう
ケースはよくあります。
その時には再度、人員削減を実施する必要が生じます。
しかし、リストラによる人員削減は1回で完了すべきです。
これが2回以上になると、自主退職者も次第に増えてしまい、本来、会社に引き止めたい有能な人材の
流出が続くと、業績回復が難しくなります。
会社が存続するためには、やはり、傷が大きくなって取り返しがつかなくなる前の段階で、リストラを
決断することが必要なのです。
□解雇選択の必要性
仮に人員削減が必要だとしても、いきなり正社員を解雇することは妥当ではありません。
まず、正社員の出向、一時帰休、希望退職や、パート・アルバイトなど非正規社員の人員削減などの
解雇以外の可能性を検討しなければなりません。
もちろんその検討に入る前に、役員の給与カット、役職者の給与カット、従業員の給与カットなどの
措置を講じるべきです。
こうした手続きを経てなお、人員削減の必要がある場合には、正社員の整理解雇を実施せざるを
得ません。
この際、大切なのは、従業員に解雇という手段も仕方がないと納得してもらうことです。
そのためには、普段から経営上の数字を公開して、従業員に会社の経営状況を把握してもらわなけ
ればなりません。
併せて、解雇に至るまでにさまざまな手段を尽くしたことを彼らにしっかり理解してもらうことも
必要です。
会社の状況もよく分からないまま、いきなり解雇されれば、当事者はもとより残された従業員も納得
できないのは当然といえます。
□被解雇者選定の合理性
整理解雇がどうしても回避できなければ、被解雇者の選定において客観的かつ合理的な基準を設定し、
これを適用したうえで整理解雇を実施する必要があります。
例えば、「満55歳を超えている社員」 という基準は、一般常識から考えても客観的といえるでしょう。
この場合、年功序列制の会社であれば、賃金が高く、(業種などによっては) 労働生産性の低い
高齢者を解雇対象者とすることになります。
従って、裁判においても「合理性がある」と判断される可能性が高いとみられます。
これに対し、「成績の良くない社員」 という基準はどうでしょうか。
会社側からみれば、会社に必要な人材を残すという意味で合理性がある基準といえそうです。
しかし、過去の判例では、 「会社の主観的判断が入り込む余地の大きい基準であるため、(解雇
対象者の選定に) 合理性がない」 と判断されたケースが少なくありません。
この場合、少なくとも人事評価における評点の低さなど、客観的な基準を適用して「成績が良く
ない社員」 であることに合理性を持たせる必要があるでしょう。
□手続きの妥当性
整理解雇の実施に当たっては、労働組合あるいは従業員に対して事前説明を行い、十分な協議を経て
合意が得られるよう努力します。
その際、人員削減の必要性を会社の会計書類等を用いて明らかにし、 「会社が今後どのような方向に
進むのか」 という将来展望を明確に示すことが重要なポイントとなります。
中期経営計画を必ず作成したうえで、人員整理を実施する時期・規模・方法などを具体的に説明する
必要があります。
業績回復への期待が持てず、ただ整理解雇を実施するだけの内容ではいけません。
一連の手続きには、妥当性が求められます。
以上、従業員の士気を低下させないリストラの進め方を検討してきました。
リストラの最終目標は会社の業績を回復させることです。
もちろん、リストラの実施に伴う一時的な「痛み」 は避けられないでしょう。
しかし、今は苦しくても、会社の将来に明るい希望を見出せれば、従業員の理解と支持は得られる
はずです。
経営者と従業員がともに「何が何でも業績を向上させる」 という強い決意をもってリストラに取り 組めるかどうか―経営者の手腕が問われるところです。
メルマガ登録(無料)はこちら
お問合せ・ご質問はこちら
労務三大トラブルの原因
新任の部長に問題があって、部下の評判がよくないといったケースに遭遇することもあると思います。
こんなとき社長は部長をもしつけるのだという姿勢を忘れてはなりません。
部長としての心構えを教えるのは、社長自身であると認識しましょう。
また経費削減と部下のアルバイト問題の関係や、社内不倫の扱いなどにも配慮しなければいけません。
■社長は部長もしつける
例えば新任の部長が、愚痴や批判ばかりして部下が困っているとします。
本当かどうか部長に確かめてみなければなりません。
社長はまず、部長にこう確かめます。
①部長の役割を知っていますか。
②部長職とは何によって評価されるのかを知っていますか。
部長とは部下を指導指揮する立場の者です。
ただし、指揮といっても、「調査をしろ」「客先を回れ」という命令や指示だけでは不十分です。
どうしたらよいのかを具体的に示してやり、部下を同行させて、部長自身が率先して範を垂れることが
必要なのだと諭しました。
また、部下がどのような成果を出してきたかが、部長の評判につながるのであって、自分自身の売り
上げを伸ばしたからといって、それを社長が望んでいるのではないとも伝えたのです。
◎悩みを聞き、解決策を考えさせる
併せて、社長も次の点を気をつけなくてはなりません。
①部長の困っていることを聞いてやること。
これはできるだけ具体的に聞かなくてはいけません。
②解決策を部長に考えさせると同時に、何か良い方法を示してやること。
③この2つを実行している社長自身の姿を部長に示し、真似をさせること。
では、一つひとつ説明をしてみることにします。
まず、①は部長の良くない状態を部長自身に分からせることです。
つまり問題をつきつめて考え、その根本を見極める機会を与えることです。
これこそが指導といえるものです。
②は①の延長線上なのですが、社長なりの代替案を伝えることによって部長は管理技術(この場合、
部下の養成が問題です)について様々な策を学び取ることができます。
③は最も重要です。手本を示し,真似るというのは何やら子供じみていますが、実はこの方法が
行動パターンを修得するのに最も良いきっかけになります。
以上、結局は社長自身が熱意と自覚(自分の役割に対して) を持って部下に接することが大切と
いうことになります。
そうすれば、その姿を部下である部長が教訓として感じとると思います。
部下と張り合ってでも、営業成績を上げたいと思っているのだから、見所はあるのだと思います。
この部長を育て上げてみることです。
□社員のアルバイトは許せるか
一口に副業といっても,好況時と不況時では性格が異なります。
好況時にアルバイトや兼業にのめり込んでいた例の多くは、生活が非常に派手だったりクレジット
カードで借金を重ねていたりといった生活破綻が原因となっていました。
ところが景気後退期に入ると、残業代やボーナスが減少したために家計が苦しくなって、アルバイト
を始める会社員が増えています。
特に少々背伸びした住宅ローンの返済計画を立てたため、苦境に陥る例がよく見られます。
アルバイトの影響いうまでもなく、遅刻が繰り返されるなど通常の職務の遂行に悪影響を及ぼすなら、
労務提供義務の不履行とみなされます。
昇給停止や減給の対象にすることもできます。
また、女子社員が風俗関係の仕事を始めた場合などにも、「会社の品位を著しく損なうため社業に
マイナス」という理由で処分することが可能です。
悪質な場合には、社員のアルバイトや兼業を強制的に辞めさせることもできます。
この他、社内の事情からなるべく穏便な形で収める必要があれば、ボーナスの査定などで格差をつける
ことも一案です。
生活設計に組み込んでいた残業やボーナスが“突然”消えてしまった深刻な状態のままでは道義上、
アルバイトを全面的にやめさせるわけにはいかないはずです。
兼業時間の上限を設定するなどの対応が現実的です。
ただ、これらの措置は現実に職務に対する悪影響が出始めて講ずることができます。
事前にいち早く対応するには、アルバイトや兼業の許可制を就業規則などに明文化し、社内に周知
させる必要があります。
職務への悪影響を防ぐため、兼業を許可制とすることは、合理的な措置とみなされます。
地裁の判例でも、会社に無断で兼職することは、警告、さらに解雇理由にもなりうるとされたものが
あるからです。
上限時間を設定することも企業側の裁量の範囲内と考えられます。
設計士やデザイナーなど専門的な知識を持っている場合、社員の兼業をある程度、黙認している
企業は多いようです。
特に専門技能がなくても早朝のビルの清掃や工事現場の誘導員といった仕事をする例が出始めて
います。
こうした動きは兼職の禁止規定がある公務員にまで広がっているようです。
いずれにしても、時短が進んで社員が自由にできる時間が増えるにしたがって、兼業の問題はより
一般的になると認識したうえで、対策を講じておく必要があります。
□社内の風紀を乱した社員の処罰は
妻子ある社員の不倫は,会社にとって社内風紀の乱れ、得意先の信用失、さらには当該社員の家族
破壊に伴う金銭トラブルなど様々な悪影響があり、黙って見過ごすことができない問題です。
しかし、不倫自体は私生活上の非行にとどまり、直ちに職場の規律秩序に違反するとはいえない
ので、取り扱いに悩んでいる経営者も多いはずです。
裁判所は、
「(勤務時間外の)私生活上の非行であっても、それによって企業の対外的取引関係あるいは
信用をき損する場合には懲戒が認められる」として企業秩序維持のための懲戒を認めています。
したがって、不倫も、「社内の男女関係が乱れている。営業マンが取引先、得意先の女性社員と
男女問題を起こしている」などの事実が企業の信用失墜に結びつくものなら、懲戒の対象となり
うるようです。
一言で不倫といっても、大学教授と女学生のケースのように、社会的非難が極めて大きい場合や、
経理社員が関与して横領などの金銭問題が生じ刑事事件となる場合もあれば、一夜のあやまちと
いったケースまでいろいろです。
交際の深浅、期間、相手方の事情、会社に対する影響などを総合的に判断することが必要です。
懲戒事由にあたる場合でもその程度として、けん責、出勤停止、降格、解雇のいずれをとるかが
決定しなければなりません。
取引先の女性社員などとの男女問題については、具体的事情によって会社の信用を極めて失墜
させるものですから、けん責以上の懲戒処分も可能です。
しかし、社内不倫は、交際それ自体は勤務時間外に、社外で行われていることですから、不倫に
関連して金銭問題その他のトラブルがない限り、直ちに社内秩序、風紀に悪影響を与え、懲戒
解雇に相当するとまではいえないことです。
もちろんその発覚については、社内の噂となったと思われますから、社内風紀に悪影響なしとも
いえません。
示しのつく、毅然とした処分をそこで、両名とも素行不良により社内風紀を乱したとして弁明を
聴いたうえでけん責処分とし、直ちに交際を中止するように勧告すべきです。
そして、男性については、今後とも同種の非行を繰り返したときは解雇することもある旨を伝え、
さらに反省の有無によっては退職の勧告、これを拒めば閑職へ配置転換するなど、他の社員に
しっかりと分かるような処分をすることが大切です。
また、女性については、直ちに金銭を扱わない部署に配置転換すべきです。
メルマガ登録(無料)はこちら
お問合せ・ご質問はこちら
労務三大トラブルの原因
| 労働条件の不利益変更 |
■不利益変更を行う際の留意点 正規の従業員とは期間の定めのない契約を結ぶのが−般的かと思われます。 右肩上がりの経済成長期においては、入社から月日がたつにつれて賃金や退職金を含めた 労働条件がよくなっていくのが普通でしたが、企業を取り巻く環境がめまぐるしく変わる 現在においては、従業員と最初に約束した労働条件を不利益に変更しなければならなくなる こともあるのが実情ではないでしょうか。 企業を発展・存続させるためには労働条件の不利益変更もやむを得ない側面もありますが、 従業員の生活にかかわる重大問題であり、一歩間違えばやる気を失わせ、企業業績を悪化 させる要因となることもあります。 やむを得ず従業員の労働条件を不利益に変更しなければならないときは、従業員との信頼 関係を保ちながら、新しい労働条件に納得してもらい、前向きに働いてもらうようにする ことが何より重要です。 そのためには、会社が一方的に通告するなど強引なやり方によって従業員との関係を悪化 させないように、手順を踏みながら変更について理解し、協力してもらえるように会社も 努力することが大切です。 いずれにせよ会社が一方的に労働条件を不利益に変更することはできません。 従業員の同意に基づいて行うことが原則です。 同意を得ないで行った労働条件の変更は無効となります。 ただし、大勢の従業員がいる場合に、一人ひとりの従業員の同意を取らないと労働条件の 変更ができないとなれば、多大な困難を伴います。 そこで、就業規則を変更することによって統一的に労働条件を変更することが例外的に 認められています。 次項からは、従業員の不利益変更を行う場合の方法や留意点を解説します。 □個別同意による不利益変更 1.個別同意による不利益変更の手順 従業員の労働条件を従来に比べて不利益に変更する場合には、その変更内容について 同意をしてもらう必要があります。 この項では、個別に同意を得るための手順を説明しますが、従業員に対して変更内容を わかりやすく説明し、十分に理解してもらったうえで、最終的には書面による同意を 取ることが目標です。 特に貸金や退職金にかかわる不利益変更については、後日のトラブルを避けるため個別の 同意書を取っておいたほうがよいといえます。 具体的な手順は次のとおりです。 (1)個別面談または、説明会を開催する 労働条件の変更について個別面談や、対象者が多い場合は説明会を開催し、 労働条件の変更の背景や必要性を含めて、その内容をわかりやすく説明します。 会社として「なぜ変更しなければならないか」を丁寧に説明し、従業員の理解 を促すことがポイントです。 (2)従業員からの質問に答える (1)の説明に対して、従業員から質問があれば、それに丁寧に答えていくことで 内容を十分に理解してもらいます。 面談や説明会の場だけでなく、その後一定の期限を定めて質問をあげてもらう ことで、理解を深める機会を設けることがポイントです。 (3)同意 提出してもらう 提出期限を設けて同意書を提出してもらうようにします。 会社からの説明を受け、納得して同意したことがわかるような内容の同意書と することが大切です。 (4)同意書を出しない従業員の対応を行う 提出期限までに同意書を提出しない従業員には、個別に話し合いの場を設け、 「なぜ同意をしたくないのか」をよく聞いて、疑問や不満などに丁寧に答え、 変更の必要性を説明しながら、ねばり強く説得を行います。 2.同意書の書式例 次に同意書の一例を示します。 □就業規則による不利益変更 個別の同意を取ることなく、就業規則に基づいて労働条件を変更することで、従業員の 労働条件を統一的に不利益変更することが可能です。 就業規則による不利益変更を行う場合には、次の項目がクリアされているかを留意する 必要があります。 (1)法律上必要な手続きが取られているかどうか (2)不利益変更に合理性が認められるかどうか (3)法令または労働協約に違反していないか (1)法律上必要な手続きが取られているかどうか 就業規則を変更するためには、 ①従業長の意見聴取が行われていること ②労働基準監督署へ届けられていること ③従業鼻に周知されていること が必要です。 ①従業員の意見聴取が行われていること 従業員の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合の意見、 ない場合は従業員の過半数を代表する者を選出したうえでその意見を出して もらい、意見書を提出してもらうことが必要です。 この場合に従業員の過半数を代表する者の選出を適正に行っているかどうかに 気をつける必要があります。 会社に指名された従業員や、たんに在籍期間が長い従業員が代表になって いないか、また、次の点をクリアしているかチェックしてみてください。 ・管理監督者ではないこと(管理監督 者は従業員代表にはなれません) ・その都度、投票、選挙などの民主的な方法で選ばれていること ②労働基準監督署へ届けられていること その事業場に常時10人以上の従業員がいる場合は、就業規則変更届に①の 意見書を添付して労働基準監督署に届け出なければなりません。 複数の事業場があるときは、それぞれの管轄の労働基準監督署に届け出ます。 ③従業員に周知されていること 就業規則の変更内容を従業員が知らないということでは、その内容は労働 条件とはなりません。 就業規則が会社の金庫のなかにしまってあったり、上司に頼まなければ見せて もらえなかったり といったことでは、万が一トラブルになったときに内容が 認められない可能性があります。 次のような方法により周知されているかチェックしてみてください。 ・常時、各作業上の見やすい場所に掲示し、または備え付けること ・就業規則を各従業員に配布すること ・パソコンなどでいつでも閲覧できるようにすること (2)不利益変更に合理性が認められるかどうか 会社が従業員の労働条件をこれまでより不利益に変更する場合は、合理性がない と認められません。 この場合に、合理性があるかどうかは、過去の判例により積み重ねられた基準に 基づき判断されます。 また、平成20年3月1日から「労働契約法(※)」が施行され、不利益変更の際の 判断基準が定められていますが、これは過去の判例により積み重ねられた判断基準 を明文化したものです。 変更の合理性については、次項で詳しく解説します。 ※労働契約法とは、労働契約についての基本的なルールを定めた法律で、 合理的な労働条件の決定や変更が円滑に行われることを通じて労働者の 保護を図り、個別の労働関係を安定させることを目的としています。 (3)法令または労働協約に違反していないか 当然のことですが、労働基準法を始めとした法令に違反する内容を就業規則に 定めてもその部分は無効となります。 また、労働組合との労働協約(※)に反する内容も認められません。 ※労働協約とは、労働組合とその組合員の労働条件について書面により定め、 相互に署名または記名押印したものです。 □不利益変更の合理性 労働契約法では、就業規則による不利益変更に合理性があるかどうかを判断する基準 として次の事項を定めています。 (1)従業員の受ける不利益の程度 (2)労働条件の変更の目的および必要性 (3)変更後の就業規則の内容の相当性 (4)労働組合等との交渉の状況 (5)その他の事情に照らして合理的かどうか (1)従業員の受ける不利益の程度 従業員の被る不利益の程度が大きい場合は、合理性があると判断されにくくなり ます。 不利益であっても軽微な程度であれば認められやすいといえます。 (2)労働条件の変更の目的および必要性 会社が不利益変更をしなければならない具体的な目的や必要性があることが前提 です。 労働条件を不利益に変更する場合、会社の経営状況が悪化しているなどの理由が 考えられますが、特に貸金や退職金など重要な労働条件の不利益変更を行う際は、 より高いレベルでの目的や必要性が求められます。 (3)変更後の就業規則の内容の相当性 不利益が一部の従業員にとって著しく不公平なものとなっている場合には、内容の 相当性が認められにくくなります。 その従業員について不利益を緩和するなどの経過措置を図ることが必要となります。 また、賃金制度は不利益変更となるが、定年を延長するなどほかの労働条件を改善 するような代替措置が取られている場合や、変更までの猶予期間が設けられている 場合は相当性があると判断されやすくなります。 (4)労働組合等との交渉の状況 労働条件の変更について従業員と真摯に話し合っているかどうかがポイントです。 労働組合や従業員代表と変更内容についての話し合いを重ね、納得してもらった うえで内容が決められたものかどうかが鍵となります。 (5)その他の事情に照らして合理的かどうか (1)〜(4)を含め、就業規則の変更にかかわる諸事情が総合的に考慮され、 合理的かどうかが判断されます。 □その他のポイント 1.個別同意による不利益変更の留意点 労働契約法では、労働条件の変更の同意は、会社と従業員が対等な立場でなされなけ ればならないと定めています。 したがって、従業員の理解を深めるために丁寧な説明を行うことが欠かせません。 「同意しないと解雇する」などと同意か解雇かを選択させるような言動はしないように しましょう。 個別同意による不利益変更を行う場合においても、就業規則の変更と同様に不利益 変更に合理性があることが求められます。 合意内容が、法令に違反していれば無効となることは当然ですが、合法であり同意書 を取っていたとしても、内容に合理性がなければ、万が一、訴訟を起こされたときに 無効と判断される可能性もありますのでご留意ください。 また、就業規則の水準を下回る内容の労働条件で個別の労働契約を行った場合には、 その部分については無効となります。 たとえば、就業規則に定められた貸金より、低い貸金を個別の労働契約で定めた 場合がこれにあたります。 この場合などは、就業規則に定められた水準に貸金が引き上げられます。 2.就業規則による不利益変更の留意点 従業員との労働契約において、特別に約束している労働条件があった場合に、それを 就業規則によって変更することはできません。 たとえば、ある従業員と就業規則と異なり「転勤はさせない」という労働契約をして いる場合に、就業規則において「すべての従業員について転勤させる可能性がある」 と変更したとしても、その従業員を就業規則の変更によって転勤させることはできません。 この従業員と約束した労働条件を変更するためには個別同意が必要です。 3.働組合がある場合 労働組合がある場合は、労働協約を締結することにより労働条件を不利益に変更する ことが可能です。 労働協約には、個別の労働契約ならびに就業規則よりも優先する特別の効力が認め られています。 したがって、労働協約により労働条件が不利益に変更された場合、これまでの労働 契約は無効となり、その労働組合の組合員の労働条件は、新たな労働協約で定めた 基準となります。 労働協約による不利益変更の効力が及ぶ範囲は、原則としてその労働組合の組合員 ですが、事業場の従業員数の4分の3以上を組織している労働組合と締結した労働協約 については、非組合員である同種の従業員に対しても適用されることがあります。 ただし、労働協約が特定の労働組合の組合員を不利益に取り扱うことを目的として 締結された等の場合は、その効力は否定されます。 なお、労働協約により労働条件を不利益に変更した場合でも、就業規則の改正と 労働基準監督署への届出は必要となります。 メルマガ登録(無料)はこちら お問合せ・ご質問はこちら |
労務三大トラブルの原因
| 労働基準監督署の調査 |
■運営方針 厚生労働省が発表している運営方針では、毎年のように、「長時間労働抑制のための 監督指導」および「賃金不払残業の防止」が重点項目として挙げられてい ます。 このような背景もあって、労働基準監督署が行う監督指導件数は増加傾向にあり、また 以前に比べて方法も変化してきていると思われます。 今回は、労働基準監督署の監督指導の現状と方法等を示しながら、対応のポイントを 説明します。 □労働基準監督署の調査の現状 労働基準監督署の調査には、労働基準法や労働安全衛生法が順守されているかをチェック する臨検監督があります。 (1)臨検監督の種類 「臨検監督」とは、通常、労働基準監督官が事業場に立ち入り、労働基準法等が順守 されているかどうかの調査を行い、違反している場合には是正のための行政指導を 行うほか、危険性の高い機械・設備などについては、その場で使用停止等を命ずる 行政処分を行うことを指します。 具体的には、次のような種類があります。 ①定期監督 労働基準監督署が、過去の監督指導結果等も踏まえ、その年の監督計画に基づいて、 労働条件、安全衛生全般について調査を行います。 以前は、予告してからの立入り調査が通常の方法と思われていましたが、現在は 原則として予告なしで突然訪問することになっているようです。 他にも、「集合監督」と呼ばれる、複数事業所を一斉に呼び出して行う方法が あります。 この方法による調査がここ数年増えており、各事業場を訪問していたものを 一斉に呼び出すことにより、効率的に監督指導できるようにしています。 ②申告監督 労働者から法令違反等の申告があったときに行われますが、事前の予告がある 場合とない場合があります。 労働者から申告があった旨は、監督官が会社から質問されても通常は伝えない ことが多いですが、事案によっては伝えることもあります。 また、指定した日時に呼び出されるケースもあります。 ③災害時監督 一定以上の労働災害が発生した事業場に対して行われ、原則として、事前の 予告はありません。 (2)実施状況 各都道府県労働局では、管下の労働基準監督署が実施した定期監督等の実施結果を 毎年発表しています。 平成30年に都内労働基準監督署が実施した定期監督等では、労働者からの情報や労働 災害の報告等を元に、前年の1万607事業場を上回る1万2668事業場が対象とされました。 調査結果では、全対象のうちの72.5%に当たる9188事業場で労働基準関係法令違反 が発覚した。 今後の指導方針として、「今後とも、労働条件をめぐる問題点を的確に把握しつつ、 効果的な監督指導を実施するとともに、法令違反を繰り返す等悪質な事業主については、 厳正に司法処分に付すこととする」と結んでいることからも、監督指導の厳しい姿勢が うかがえます。 (3)重点項目および監督対象となる事業場 都道府県労働局は、厚生労働省が毎年策定している「地方労働行政運営方針」を踏まえ、 局内の管内事情に則した重点課題を盛り込み、都道府県労働局ごとに行政運営方針を 策定して、計画的な行政運営を図ることとしています。 したがって、この内容をチェックすることにより、その年の監督業務の重点項目の 概要を把握することができます。 また、監督実施先としては次のような事業場が対象となります。 ①近年の労働環境の状況や監督結果から問題があると思われる業種及び事業場 ②特別条項付き36協定(※)を届け出ている事業場 ※事業や業務の態様によって、臨時的に特別の事情により、36協定で延長 できる限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない場合に、これを 一定の条件の下で可能にするのが36協定に設ける「特別条項」です。 ③自主点検(※)の結果、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因する ものを除く。)の認定基準について」を考慮して調査が必要と思われる事業場 ※36協定に特別条項がある場合、その時間の長さによって、「労働条件等自主 点検報告書(労働基準関係法令等の順守状況を自ら点検し、その把握した 問題点に応じ自主的な改善を図るもの)」等の書類が送付されてきます。 点検の結果、現実に長時間労働を行っている事業場の場合は、監督指導が 入りやすいと思って間違いはないでしょう。 特に、労災保険の過労死認定基準には留意することが大切です。 また、この自主点検結果を報告しない場合は、違反している可能性が高いと 判断され、監督指導の対象になると考えたほうがよいでしょう。 (4)監督官の権限 このような監督を行う監督官の権限は労働基準法で次のように定められており、 第101条では行政監督権限、第102条では捜査権や逮捕権も有する特別司法警察 職員としての役割まで規定しています。 □労働基準監督官が交付する書類 調査で問題があると、労働基準監督官から書類が交付されます。 主なものは是正勧告書、指導票、使用停止等命令書といったものです。 (1)是正勧告書 労働基準監督官が労働関係法令違反があると認めたとき、使用者に対して是正 勧告書を交付します。 事業主または労務担当者等は受領年月日を記入し、記名・押印をします。 是正勧告書には違反事項と是正期日が指定されており、期日までに是正する必要が あります。 是正勧告は行政処分(行政機関が国民に対し、法規に基づいて権利を与えたり義務を 負わせたりすること)ではなく、行政指導にあたり、使用者はこれに従う法律上の 義務を負いません。 是正勧告に従って行う改善は、あくまでも任意の協力によってなされているものです。 しかしながら、労働基準法等の違反状態を放置すれば、司法処分に付される可能性が あり、間接的な強制力を持っていると考えられます。 (2)指導票 指導票は、労働基準法等に直接違反するものではないが、指針やガイドラインに 基づいて改善すべき事項を記載して、使用者に対して交付する文書です。 また、法令違反と断定しがたいが改善すべきこと、あるいは改善の方法について 記載されている場合もあります。 (3)使用停止等命令書 施設や設備に安全対策上の不備があり、労働者に急迫した危険がある、と認められる 場合等で緊急を要するものについては、通常は労働基準監督署長名で「使用停止等 命令書」を交付します。 使用停止等命令は行政不服審査法第2条にいう行政処分に該当しますので、その 命令に従わない場合、罰則の適用もあります。 □対応のポイント (1)突然の来訪への対応 監督官は1人で来ることが多く(地域や案件によっては複数の場合もあり)、 一通り会社概要を聞いたうえで、本題の質問や書類等のチェックをしていくケース が多いようです。 担当者不在の場合や社会保険労務士に給与計算や労務部門を委託している場合は、 「後日訪問し、書類等はその際に提示する」等の対応でもよいかと思われます。 監督指導に関しては、統一した基準に基づいて行われますが、対応は監督官の裁量 による部分があるというのが、一般的です。 書類に関する調査の仕方では、担当者が不在の場合でもタイムカード等わかる範囲で 何かしら回収していく場合があり、ケースバイケースといえます。 (2)是正期日 是正勧告書には、是正すべき期日が記載されていますが、項目によって「即時」と 記載されたり、「○月○日」と大体1カ月程度後の期日が指定されたりします。 「即時」については、例えば「36協定が締結されていないにもかかわらず時間外 労働をさせている」等、即時に是正しないと法違反を放置することになるという ような項目が挙げられます。 また、期日が指定されている項目については、期日までに完全に是正処理ができない 場合もあるでしょう。 もちろん期日までに是正するのがベストですが、努力しても時間的に厳しい場合は、 期日までにできる内容とできない内容を整理して、できない内容については現在の 取組み状況と今後の見通しを説明して、前向きに対応している姿勢を示すことが 大切です。 監督官に納得してもらえれば、期日の摩期をしてもらえるケースもあります。 (3)遡及支払い 是正内容で多い項目の1つとして、「残業代の未払い」が挙げられますが、適正に 割増貸金(時間外労働、休日労働、深夜労働)が支払われていない場合、不足分の 遡及処理が発生します。 未払い貸金の時効は2年間ですが、事案によって異なります。 明確な基準はないものの、大体3カ月から半年程度遡及して支払うケースが多い ようです。 ただし、悪質な場合は2年間の遡及もあり得ると考えたほうがよいでしょう。 (4)是正内容を放置または虚偽の報告をした場合 労働基準監督署による是正勧告書の交付は行政指導ですので、会社はこれに従う義務は なく、また、指導内容につき改善しないことに対する罰則もありません。 ただし、勧告書に記載されているのは労働基準法等の法令に対する違反内容であり、 各違反項目に対する罰則が労働基準法等に成定されていますので、結果的には司法処分 を科されることもあり得ます。 前述した通り、労働基準監督官には特別司法警察職員としての権限がありますので、 是正内容に従わず放置したり繰り返し指導・勧告を受けたり、総合的に見て悪質な場合は 送検される可能性もあります。 また、実際には改善していないのに改善したと虚偽の報告をすると、労働基準法第120条 の罰則が適用されることとなり、悪質と判断されます。 (5)重要なチェックポイント 調査でチェックされやすいという視点のみならず、法的にも労務管理面から見ても 注意が必要なポイントは次の通りです。 ①36協定・就業規則の届出、周知および労働者代表の選任方法は適正か ②36協定ほ限度基準に適合しているか ③割増賃金の支払いは適正か ④法定休日の確保はできているか ⑤年次有給休暇の付与(パート労働者等も含め)は適正か ⑥労働条件通知書を交付しているか ⑦安全・衛生委員会等の設置、衛生管理者・産業医の選任 (常時50人以上の 労働者を使用する事業場)を実施できているか ⑧長時間労働者への面接指導を実施できているか ⑨定期健康診断を実施できているか □最後に 厳しい雇用情勢が続く中で、残念ながら賃金不払い残業や長時間労働にまつわる労使間の トラブルは増え続けています。 今後、調査の傾向が変わることも十分考えられます。 大切なことは、「調査ありき」の対策や整備ではなく、調査の有無にかかわらず基本的な 労働法令を順守すること、たとえ監督指導が入り是正勧告を受けたとしても、慌てずに その指導に従い改善することです。 労働条件や労働環境の改善にかかる法令順守、それこそが有能な人材の確保および定着に つながり、ひいては会社業績の発展につながることは間違いないのです。 メルマガ登録(無料)はこちら お問合せ・ご質問はこちら |
労務三大トラブルの原因
| 労務トラブルの事例 残業・退職・解雇 |
|
社内ルールが整備されていないことにより、契約内容があいまいなまま採用してしまい、 特に残業代を含んでの契約の場合、給与のうちいくらが残業代なのか、何時間分なのか 事前の防止策として、「コンプライアンス(法令遵守)経営」をいかに確立するかが企業の しかし、確かにコンプライアンスなどルールを守ることも大切ですが、それ以上に「不祥 そのため、常に透明感のあるガラス張りの経営を心がけ、社員みんながチェックできる 労務管理は人が相手だけにとてもデリケートです。 ちょっとしたボタンの掛け違いが後で尾を引きます。 労働者個人が直接裁判所に労使問題を持ち しかし、会社がいくら誠意を尽くしても、労使間 もちろん、労使間の話し合いによって自主解決に至ればいいのですが、どうしても解決 ここでは労務の3大トラブルである「残業」、「解雇」、「退職」について事例解説します。 |
| 残業問題 |
|
36協定なしでは残業や休日出勤を命令できず、もし残業をさせ残業手当を払った ・ 残業、休日出勤の具体的理由 ・残業、休日出勤の対象となる業務の種類 ・残業、休日出勤する労働者の数 ・残業できる時間 最長で1年間(有効期間が過ぎれば、「自動的に」無効になる)なので更新を忘れない ○36協定なしで残業、休日出勤した場合 ・「6ヶ月以下の懲役、または、30万円以下の罰金」となっています。 ・残業、休日出勤を命じた部課長など(現場の責任者)、会社・社長の責任を取 労働基準法(36協定)では、 ○1週間で最大に働くことのできる労働時間・・・40時間 ○1日で最大に働くことのできる労働時間・・・・8時間 としています。 しかし、現実には残業はあり、労働時間の範囲を超えるため「所定の手続き」をとれ これを所轄の労働基準監督署に届け出るのですが、36協定を出していない会社は しかし、コンプライアンスが重視される現在、たとえ中小企業であってもこの間題を 労働基準法が改正され、より厳格な時間管理や残業代支給の運用が求められてい 残業代の未払いやその計算方法の間違いが指摘されると、企業は過去2年間遡っ これは、企業にとって一時的に大きな出費となるだけでなく、「法律違反」を行っていた これは100万円以上の割増賃金の支払いを命じられた企業のみの統計であり、それ インターネットなどで誰もがこのような情報を得ることができるようになった今の時代、 いわゆる「名ばかり管理職」の問題です。 現在、通達や裁判例から、次のように管理監督者は定義されています。 管理監督者の範囲について、「経営と一体的な立場にある者の意であり、これに該当 2008年の1月にマクドナルドの管理監督者をめぐる判決が労働者側の勝訴となり、 賃金を支払わない、というケースが多々みられ、労使の間の紛争になっています。 管理監督者に関しては、旧労働省が昭和22年に通達を出しています。 1.経営者と一体的な立場 2.労働時間が管理されない 3.管理職としてのふさわしい待遇 以上の3点です。 ・会社の経営方針の決定過程に参加しているか。 ・出退勤は自由か、会社から管理されていないか。 ・採用権限は有しているか ・職務の重要性にふさわしい十分な役職分の手当てが支給されているか。 ・管理下にある部下の人事権を有しているか ・仕事内容が管理監督者としてふさわしいか。 (1)経営方針の決定に参画、または労務管理上の指揮権限を有しているか (2)出退勤について厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について自由裁量を (3)職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか (4)給与・賞与等について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか
厚生労働省は、「賃金不払残業」の解消を図るために、次の 各企業はこれを参考に具体的な対策を立てていくことが必 (1)労働時間の適正把握に関する基準の遵守 賃金不払残業の背景には、職場の中に賃金不払残業が こうした土壌をなくしていくため、労使は、次に掲げるような ・経営トップ自らによる決意表明や社内巡視等による実態の把握 ・労使合意による賃金不払残業撲滅の宣言 ・企業内又は労働組合内での教育 賃金不払残業が行われることのない職場を創るためには、職場において適 できれば客観的な記録が残り、処理も行いやすいタイムカードなどのシステム 労働時間を適正に把握し、賃金不払残業の解消を図るためには、事業場ご さらに、相談窓口を設置する等により賃金不払残業の実態を積極的に把握す
労働契約法では「労働契約は当事者の合意により変更することができる」(労働契約 労働条件の変更を行う場合は、会社は必ず給与規程などを整備し、社員全員に説明を ①社員の受ける不利益の程度 ②労働条件の変更の必要性 ③変更後の就業規則の内容の相当性 ④労働組合等との交渉の状況 ⑤その他の就業規則の変更に係る事情 上記①〜⑤の事情を検討し、それが合理的である場合は就業規則の不利益変更も認
|
|
しかし、退職時には、労働者が退職証明書などを求めない限り、退職する労働者と会社 しかし、労働者が退職する際は、会社側は当然「いつ」「誰が」「どのような事由で」退職 後々、退職事由や退職日などをめぐってトラブルとなることは少なくありません。 1つめは「自己都合退職」、2つめは「解雇」、そして3つめが「会社都合の同意退職(退職
自己都合退職とは、その名のとおり社員自らの意思によって退職することです。 自己都合退職の場合は大きなトラブルになることは少ないと考えられますが、それでも ・退職理由が「自己都合退職」であること ・退職日および実際の最終出勤日 ・重要な引き継ぎ事項 社員の退職が成立するのは、本人が会社に退職の 「会社が認めた時」とは、一定の権限者に退職の 正式に会社の人事権限者まで伝わっていないケースでは、その退職は正式に決定した ただ、「言った、言わない」となってしまうことも少なくないため、やはり書面で退職
自己都合退職に対して、解雇は非常に大きなトラブルになることがあり、会社としては 解雇とは会社からの一方的な契約解除をいい、労働者の同意を得ないものです。 そのため解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められな この解雇事由は、想定される事由はできるだけ多く列挙し、また、その後も事例が発生 実際に解雇を行う場合は、その解雇事由と解雇日、そして解雇通知日を明確にした解
会社都合退職といえば解雇と思いがちですが、実は退職勧奨という方法もあります。 退職勧奨とは、会社が社員に「退職をして欲しい」とお願いし、それを社員が受け入れ、 「同意退職」であることが、会社からの一方的な労働契約解除である解雇とは大きく違 解雇の場合に元社員が解雇理由に納得しなければ、裁判所などに「解雇無効」を訴え 会社はその解雇が「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である」ことをプロ 万一、解雇した社員が解雇無効で会社を訴え、それを裁判所が認めた場合(不当解雇 解雇はあくまでも最後の手段と考えるべきです。 なお、退職勧奨は会社都合の退職になるので、退職した労働者は「解雇」の場合と同じ また、勤続年数にもよりますが、基本手当が受給される期間も自己都合退職の場合よ どうしても社員に退職してもらわなければいけない場合は、これらのこともしっかりと なお、退職証明書とは、上記退職書類とは別に、退職者が会社に請求することができ この請求に対して、雇用していた会社は、できるだけ早く退職証明書を発行する義務が
退職時には、上記で紹介した書類の他に「覚書」や「誓約書」といった形式で、退職後 これについても「義務」ではありませんが、後々のトラブルを防ぐためにも会社としては 退職後も会社に迷惑をかけるような行為をしないという約束を交わす書類です。 退職時の誓約書として書いてもらうこともあります。 ・秘密情報の保持 退職後も、仕事上知り得た秘密情報を保持し、開示しないという誓約 仕事上取り扱った事項の著作権、その他の権利が会社にあるという確認 退職後、同業他社への就職などを一定の範囲で制限するという確認 退職者と本人との間に、お金の貸し借りなどの紛争が−切ないことの確認 退職後も、会社の名誉を傷つけるようなインターネットへの投稿や発言などを よって重要な書面には、本人の自筆の署名と捺印を求めるべきです。 |
| 解雇問題 |
|
社員からの意思表示でなされる退職や、一定の年齢がきて退職となる定年退職とは区別 しかし、この解雇を巡り、しばしば使用者と労働者の間で争いが生じます。 個別労働紛争解決制度(注)の利用状況で、平成18年度の民事上の個別労働紛争に関
会社は社員を解雇しようとする場合、 (1)30日前には解雇する旨を伝える ○この30日はカレンダー通りで計算 ○実際の労働日、有給休暇で休んだ日は関係ない(単純に30日前) ○解雇を伝えた日は30日にカウントしない(初日は不算入) ○30日前に解雇を予告しない場合、解雇予告手当は解雇日に支払う ○即日解雇の場合が該当 ○15日前に解雇を予告する ○解雇予告手当15日分を支払い、15日後に解雇 解雇の意思を社員に伝えたら、自動的に30日後
○天災などで事業の継続が不可能になった場合 ・地震、洪水など ・窃盗、横領、傷害などの罪を犯した ・賭博などの行為 ・採用時の経歴詐称 この2つの場合、解雇を事前に伝える必要は ただし、解雇前に労働基準監督署の認定を受ける必要があります。 ○日雇いの人 ○2ヶ月以内の短期の契約社員 ○出稼ぎ労働者(4ヶ月以内の契約で働く人、いわゆる季節労働者) ○試用期間中で、入社して14日以内の人 ○解雇する理由を説明し、弁明する機会を与えなければ、解雇できない ○解雇する理由を記載した解雇理由証明書を交付する ○就業規則に解雇となる理由を詳細に記載する ○解雇に至るまでの社員と会社の対応を記録する ○事前に解雇の理由を社員に通知 ○遅刻、早退の回数と注意、指導の状況 ○仕事のミスの内容、事後対応、改善されない事情 ○反省文や始末書等の文書の保管 ○問題の発言が多い ○短期間に多くの問題を起こしている ○度重なる指摘、注意、警告に関わらず改善できない ○問題行動が就業規則の解雇理由に該当することを伝える ○問題行動があったら、日時、内容を記録する ○注意等に対する対応を記録する ○処分を行う場合は文書等で行なう ○ある程度の期間は辛抱し、証拠を積み上げる ○最終判断を下す時は、厳しい態度で望む ○感情的にならない 争いになったとき、就業規則の内容の甘さや感情的な対応が敗因となるのです。 社員の解雇ほど厄介な問題はありません。 しかも解雇する社員と経営者だけの問題にとどまりません。 企業外の労働組合はひとりでも自由に加入できますので、たとえ組合のない企業でも、 あまりにも強引で不合理な解雇は、他の社員へ悪影響を及ぼします。 簡単に社員を解雇するなどと思われては、組織の運営上好ましくありません。 解雇についてのトラブルは、実のところそのほとんどが、経営者と社員の人間関係 まず、以下の点についてチェックしてみてください。 ①社員に会社のルール(社員の評価制度や就業規則)、規則を理解してもらっ ②常日ごろ円滑な労使関係は維持されているか? メルマガ登録(無料)はこちらから
|

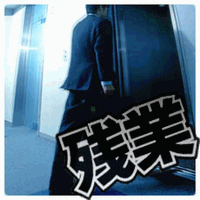
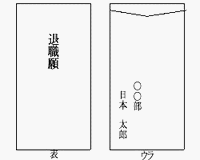
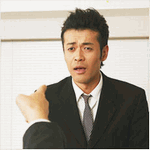
労務三大トラブルの原因
未払残業代訴訟リスク
| 未払残業代訴訟リスク |
| ■未払残業代の訴訟リスク 過去の残業代が未払いになっているとして、従業員や退職者が会社に請求をしてくる 厚生労働省では、労働局や労働基準監督署に労働相談コーナーを設け、労働者からの また、全国の地方裁判所における労働関係訴訟や労働審判の件数も増加しています。 このように労働者からの行政への相談や訴訟が増加する背景には、 ・より良い条件を求めて転職する労働者が増加してきていること ・法律にのっとった労働条件で働くことは当然の権利であるとの風潮が などがあげられます。 また、近年「貸付金利の過払い金請求」を多く手がける弁護士が増加していましたが、 これは、未払いとなっている残業代がある場合に、依頼を受けた弁護士が本人 この場合には、会社に過去2年分の未払残業代に加えて、同額の付加金請求を求め なぜなら、労働基準法に「貸金は2年間請求できる」「未払いの貸金があった場合には、 つまり、未払いとなっている残業代に付加金が加わり、未払額の倍の請求をされる 会社は、このような最悪の事態を招かぬように、残業代が未払いとなる可能性がある 次項からは現状把握と予防策について解説します。 まずは、現状を正確に把握し、未払残業が認められた場合には、早急な対策を講じる 残業代と密接に関係する部分について一つひとつ点検しましょう。 (1)基本 残業代を適正に支払うためには、まずは、会社が従業員の労働時間を正確に 労働時間の適正な把握について厚生労働省の指針では次のように示されて ①責任者が、自ら現認することにより確認し、記録すること ①は、責任者が自ら従業員の始業と終業を把握し、出勤簿に記録する方法で、 ②は、従業員自らがタイムカードやICカードにより記録し、必要に応じて残業 前項に示した方法で適正に記録されているか、また、次のようなことが行われて ひとつでもチェックが入った場合は、誤りですので、早急に対策を講じましょう。
◎チェック □出勤簿が毎日ではなく、給与締切日の間際になってまとめて作成されている。 □所定労働時間は定時なので、基本的に始業終業時刻を記録していない。 □タイムカードを始業時のみ打刻し、終業時は打刻していない。 ⇒解説③ □タイムカードに打刻された時間と、実際の労働時間に相当の帝離がある。 □タイムカードは定時に打刻させており、その後に残業をさせている。 □毎日30分未満の労働時間は切り捨てるルールとなっている。
①正確な時間把握が困難になります。出勤簿は毎日記載する必要があります。 ②定時であっても記録は必要です。 ③労働時間の把握ができず、訴えられた場合に実際より長い労働時間とみな ④実際には労働していない時間も労働時間とカウントされるリスクがあります。 ⑤労働時間の適正な把握ができません。未払残業が生じます。 ⑥日々の労働時間は1分単位で把握することが必要です。切り捨てては (1)基本 労働基準法では、労働時間について次のように定めています。 ・1日の法定労働時間 =8時間 ・1週間の法定労働時間 =40時間 この法定労働時間を基本として、会社は労働者の労働時間を管理しますが、残業や 割増貸金は、次の算式で計算します。 割増賃金=1時間当たりの賃金×割増率 なお、割増率については次のとおりです。 また、月60時間を超える時間外労働については、平成30年より法定割増率が 中小企業においても猶予措置の廃止に伴い、月 60 時間を超える時間外労働の 前項に示した考え方にのっとって、正しく残業代が支払われているか、次のような ひとつでもチェックが入った場合、それは誤りですので、早急に対策を講じ □従業員には残業代を支給しないことについての合意を得ているので大丈夫。 □年俸制になっているから、残業代は支払わなくてもよい。 □歩合給は残業代の計算基礎としなくてもよい。 □残業は命じていないから残業代の支払い義務もない。 □管理職に残業代を支払わなくても当然である。 □残業時間に上限を設けているので、上限を超えた時間は認めなくてもよい。 ①従業員の合意を得ていても労働基準法に違反しますので、合意事項は ②年俸制であっても残業すれば残業代の支払いは必要です。 ③歩合給も残業代の計算をする際は基礎に含めます。 ④実際に行ってしまった残業については、残業代の支払い義務が生じます。 ⑤管理職なら誰でも残業代を支払わなくてよいことにはなりません。 ⑥このような場合も実際に行った残業については残業代の支払い義務が 現状が把握できたら、早急に予防策を講じていくことが重要です。 その際には、雇用契約書や就業規則などの根拠書類も併せて整備していくことが 以下では、予防策を解説するとともに、就業規則などの規定例を示します。 労働時間の把握は、会社が行わなければなりません。 労働時間の把握がいい加減になっていたり、そもそも行っていなかったりした場合は、 このような場合に、全面的に従業員の主張が認められる可能性もあり得ますので 会社と従業員の両方が記録しあい照合する方法や、タイムカード、ICカード ただし、タイムカード等に打刻する場合、すぐに業務を行わないにもかかわら このようなことのないよう始業・終業の時刻を打刻するように指導・徹底する また、自己申告による労働時間の把握については、一般的にあいまいな労 自己申告による方法を導入している会社においては、労働時間の実態を正 第○条(労働時間の管理) 労働時間を適正に把握するためには、労働時間管理の責任者を明確にしておく そして、責任者に管理の権限を与え、労働時間の適正な把握がなされているか、 ただし、従業員の自己申告による時間管理の場合に、責任者が自らの部門の そのような不正が行われていないか、人事や総務部門などが、責任者の管理を 第○条(時間管理費任者の義務) 前述のとおり、労働基準法は、1日8時間・遇40時間を法定労働時間としていますが、 変形労働時間制度など業務に合った労働時間制度を導入することによって、効率的 この制度を「変形労働時間制」といい、1カ月単位、1年単位、1週間単位などの 変形労働時間制を導入することによって、変形期間内の繁忙期に応じて、所定 「フレックスタイム制は、1日の所定労働時間の長さを固定的に定めず、1週、 フレックスタイム制は、従業員のそれぞれの業務の必要性に応じて効率的な 労働時間の算定が困難な業務や業務の遂行方法を従業員の裁量に委ねる必要 みなし労働時間制には、「事業場外労働に関するみなし労働時間制」、「専門 導入するためには、それぞれ要件があり、それをクリアする必要がありますが、 そもそも実際に残業がなければ、未払残業代も生じる余地がありません。 所定労働時間内に効率的に仕事を行い、無駄な残業をなくすことがポイントです。 組織全体で残業削減に取り組むことを検討してみましょう。 残業は、責任者の業務命令があったうえで行うものです。 残業の必要性を従業員個人の判断に任せるのではなく、事前に責任者に届 残業承認書には、「残業予定日」「時間数」「業務の内容」「必要性」などを記載 これは、責任者と部下が仕事の内容や進め方などをお互いに把握し、効率的に 第○条(残業の事前承認) このような日や週を設けることで、従業員の残業に対する意識を変えさせ、集中 場合によっては、全社一斉ではなく、業務の状況に合わせて、部門ごとに設定 手に運用するためには、ポスターなどを掲示したり、人事担当者が職場を巡回 作業手順や職場のレイアウトを見直し、効率的に仕事が行えるようにすることで、 具体的には次のような方法が考えられます。 ・要員配置の見直し(業務の繁閑に応じて部門間の応援などをします) ・業務を分散させる(パートや派遣を活用したり、アウトソーシングしたり ・多能化を進める(従業員が複数の仕事をこなせるようにします) ・標準時間を設定する(各作業について標準的な時間を設定し、それを ・業務計画表を作成する(週間・月間などの業務計画表を個人ごとに また、従業員が「計画−案行−チェック−改善」といったサイクルをつねに念頭に 労働時間や雇用契約の実態が、雇用契約書や就業規則と合っていないケースが たとえば、年俸制を導入している会社で、「年俸額には残業代が含まれています」 この場合には、年俸額の全体が残業代を計算する際の基礎額に算入されます。 雇用契約書には、年俸額の内いくら分が何時間分の残業手当に相当するかといった 導入している労働時間制度が就業規則に正しく定められているか、従業員の労働
|
労務三大トラブルの原因
定額残業代制度
| 定額残業代制度 |
| ■定額残業代制度について 残業代対策の一つの手法として「定額残業代制度」があります。 この制度は、「給与支給総額の中に、一定の残業代が組み込まれている」という また、現実的に社員に対して支払っている支給総額(基本給+各種手当+残業 ただしこの場合、実際の総支給額には一定時間の時間外労働時間が含まれてい 方法としては、雇用契約上で「月給は○○円、定額残業代手当は××円」とし、「定 もちろん、雇用契約者へ制度についての十分な説明を行った上で雇用契約を結 これにより、月々発生した○○時間分の時間外労働割増貸金は取り決めた給与支 よって、月々に発生する実際の時間外時間が、当初設定した額より常に多けれ また、職種や業種によっては本制度導入が適さない場合もありますので、導入検 定額残業代は手当として設定する時と基本給に含む方法がありますが、基本給 月額30万円、月の労働日数は21日、月の残業時間は20時間とします。 1日8時間勤務×21日で月168時間の所定労働時間となります。 それに対し、時間外割増貸金は30万円÷168時間×1.25倍で約2,233円。 これが残業1時間あたりの割増貸金です。 そして毎月2,233円×20時間は44,660円。これが月間の残業代となります。 通常は、この44,660円が基本給の30万円に加算され支給されるのですが、定 つまりこの場合、30万円から44,660円を引いた255,340円が基本給となります。 もちろん給与明細書には基本給255,340円と定額残業手当(名称は他でもよ 定額残業代の計算例 判例では定額残業代については「定額である点で労基法第37条の趣旨にはそぐ つまり、残業代は基本給や手当に含まれていると言う口約束ではなく、労働契約 最近の最高裁判決では、定額残業代込みで月額基本給を定めることは法的に認 労働時間管理が不十分な企業が導入した場合には、労務トラブルが多発する傾 本制度は、事業主が従業員に支払うべき時間外割増賃金を削減することが目的 とはいえ、現実的に定額残業代制度の設定時に給与総額を上げて対応できれば その場合、従来からの従業員にとっては基本給と定額残業代を分ける方法で導 同意を得ることなく進めた場合、労務トラブルに発展する可能性がありますので、 本制度の導入の本旨としては、設定した残業時間内で仕事が完了できるよう、労 この点を忘れないようにすることが肝要です。 実際に導入する際には、社会保険労務士等の専門家に相談されることをおすすめ
|
労務三大トラブルの原因
| パワーハラスメント |
| ■パワーハラスメント 職場のパワーハラスメントを「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係 1.パワーハラスメントの定義と基準 厚生労働省では、パワーハラスメントを「職場のパワーハラスメントとは、同じ 実際、パワーハラスメントといわれる事案の中には、「その程度で“パワハ 人によってパワーハラスメントの基準が大きく違うことが原因ですが、企業とし そこで、実際に裁判で争われているパワーハラスメントがどれほどのものなの パワーハラスメントに起因する自殺が初めて労働災害として認定されたのが 上司の発言などにより医薬品の営業を行う部下の受けた心理的負荷は社会 「静岡労基署長(日研化学)事件」で問題となった上司の発言は、 ・存在が目障りだ。居るだけでみんなが迷惑しとる。 ・車のガソリン代がもったいない。 ・何処へ飛ばされようと俺は(営業担当者について)仕事しない奴だと言い ・おまえは会社を食いものにしている。給料泥棒。 ・おまえは対人恐怖症やろ。 ・誰かがやってくれるだろうと思っているから、何にも堪(こた)えてない ・病院の回り方が分からないのか。勘弁してよ。そんなことまで言わなきゃ ・肩にフケがベターと付いている。おまえ病気と違うか。 パワーハラスメント防止規程を従業員に周知することで、従業員はそれを順守 また、パワーハラスメントが生じた場合、被害者が企業に損害賠償請求を求め そうしたケースの多くでは、「企業の労務管理」が問題になりますが、パワーハ 実際にこうした規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受ける
お問合せ・ご質問はこちら |
労務三大トラブルの原因
| 個別労働紛争解決制度(平成26年度) |
| 個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然 総合労働相談の件数は7年連続で100万件を超え、減少はしていますが、高止まりを 1.総合労働相談の状況 平成26年度の総合労働相談件数は、1,033,047件(前年比1.6%減)で、うち なお、民事上の個別労働紛争相談の内訳は、「いじめ・嫌がらせ」が62,191件 また、紛争の当事者である労働者の就労形態をみると、「正社員」が91,111件 助言・指導申出件数は、前年に比べ553件の減少(前年比5.5%減)で9,471 また、あっせん申請件数は、前年に比べ702件の減少(前年比12.3%減)で 助言・指導内容の内訳をみると、「いじめ・嫌がらせ」に関するものが1,473件 なお、あっせんの申請件数では、「いじめ・嫌がらせ」に関するものがで最多、
お問合せ・ご質問はこちら |
労務三大トラブルの原因
| セクハラ・マタハラの防止 |
|
1.セクシュアルハラスメント (1)対価型セクハラ (2)環境型セクハラ 企業のセクハラ対策の基本は「セクシュアルハラスメント防止規程」の策定と セクシュアルハラスメント防止規程には、セクハラ指針の内容を踏まえつつ、
1.マタニティーハラスメントとは てまとめています。 企業に求められるマタハラ対策の内容は次の通りです。 企業に求められるマタハラ対策で示されているように、マタハラはセクハラな 防止規程」の策定と徹底であることを考慮すれば、セクハラとマタハラの防止 実際にこうした規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受ける
お問合せ・ご質問はこちら |
労務三大トラブルの原因
| セクシャルハラスメント(セクハラ) |
■セクシャルハラスメント(セクハラ) セクハラで会社が責任を取るのは職場内(就業時間中かどうかを問わない)や出張先 飲み会(会社が主催の場合や会社が主催でなくても社員がほとんど出席する)で セク 第〇条 セクシャルハラスメントは、同じ職場に働く従業員の働く意欲を阻害し、 なお、セクシャルハラスメントの相手方については、異性のみならず、同性も 2.セクシャルハラスメントとは、相手方の意に反する性的言動で、それによって (1)人格を傷つけかねない、又は品位を汚すような言葉遣いをすること (2)性的な関心の表現を業務遂行に混交させること (3)ヌードポスターや卑猥な写真及び絵画類等を見ることの強要や配布又 (4)相手が返答に窮するような性的な冗談やからかい等をすること (5)私的な執拗な誘いを行い、又は性的な噂若しくは経験談を相手の意に (6)性的関係の強要、不必要な身体への接触又は強制猥褻行為等を行う 3.従業員は、他の従業員の性的な言動に起因する問題により被害を受けた場 これらの申立てを受けた者は、速やかにその旨の報告、事実関係の調査に なお、相談窓口担当者以外の従業員が、同様の相談を受けた場合、本人の ①社内報などの広報資料にセクハラの具体的内容などを記載し、配布する ②セクハラのイメージは個人によって異なるため、 ・セクハラ防止の社員研修などを行なう ・法的に懲罰を受ける行為であることを周知する ○懲罰委員会の開催 ○相談窓口の設置 ○被害者へのカウンセリング ○外部専門家との提携(弁護士、社会保険労務士、産業医など) たとえば、相談者などのプライバシーを保護するために、別室でヒアリングなどを
お問合せ・ご質問はこちら |
労務三大トラブルの原因
| 管理職と管理監督者 |
| ■管理職と管理監督者 『管理職だから残業代は支払わなくていい!!』と思っている中小企業経営者も少な 確かに、管理監督者であれば、労働時間・休憩・休日に関する規定を適用しないと ですから残業しても、休日労働しても、休憩しなくても、割増賃金の支払は必要ありま ただし、 「管理監督者」については、肩書きや職位ではなく、その労働者の立場や権限を踏ま 現在、残業代等を支払われていない管理職の方はいませんか? 労基署の調査などにより、管理監督者でないと判断された場合は、過去にさかのぼっ ・社内での管理職:部長、次長、課長、係長、店長など肩書がある者。 ・労働基準法上の管理監督者:労働条件の決定その他労務管理について経営者 ●労働基準法上の管理監督者は実態的に判断される 管理監督者といっても労働者であることには変わりありません。 しかし、管理監督者は経営者に代わって同じ立場で仕事をする必要があり、 経営者と一体的な立場で仕事をするためには、経営者から管理監督、指揮 一方、「課長」、「リーダー」といった肩書きであっても、自らの裁量で行使 また、営業上の理由から、セールス担当の労働者全員に「課長」といった肩 管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応を求められることがあった このような事情から、管理監督者の出退勤時間は厳密に決めることはできま また、勤務時間の制限がない以上、出退勤時間も自らの裁量に任されてい 遅刻や早退をしたら、賃金や賞与が減らされるような場合は管理監督者とは 管理監督者はその職務の重要性から、地位、賃金その他の待遇において一 ●管理監督者であっても深夜割増賃金・年次有給休暇は適用される また、年次有給休暇もー般労働者と同様に与える必要があります。 ●管理監督者でも労働時間の把握は必要。 また、会社には安全配慮(健康に配慮する)義務がありますので出退勤時 長時間労働は健康障害を引き起こす恐れがありますし、労働安全衛生法
|
お問合せ・ご相談はこちら
企業運営に欠かせないマーケティング、業務改善、リスクマネジメントの3つの仕組みづくりを
倒産に見舞われています。「知っていれば」「対策を講じていれば」倒産を防げたはずの企業が多く存在する
ことを、私たちは数多く見聞きしています。
事業運営に欠かせないマーケティング、業務改善、リスクマネジメントの分野で全力を尽くして支援して
まいります。
| 対応エリア | 静岡・愛知県内、東京周辺 |
|---|
