〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町2-26-501
組織人としての基本動作とは
■基本動作は企業経営の原点
企業の経営管理の成否は管理プロセスが 円滑に機能しているか にかかっている。
プロセスが機能するとい うことはそれを構成する業務一つ ひとつがうまく運営されていることに
かかっているが、この運営は結局は人の問題です。
基本動作とは、この人が企業で活動する ために意識して行わな ければならない行動の基本である。
ここで取り上げる実例は「あいさつ」「電話」。
「あいさつ」も「電話」も外部との接点にあり、企業の顔であり、心を通じ合う入口です。
□職場でのあいさつはリズムとスピードと活力を生む
心は形に表れ、形は心を律する。形直ければ影正し、礼は美しい心の衣装である。
今年も新卒者が誕生しているが、豊かな時代に生まれ育った子供たちが社会人になりました。
「あいさつも満足にできない」 と上司・先輩は嘆いている。
文部省の児童調査によると、近所の人にあいさつをしない子供が増えており、学校教育に一番望む
ことが 「しつけ」であるという。
どのように時代背景が変わっても、変わらないのはあいさつを始めとした基本動作です。
1.あいさつとは
(1)相手の立場を尊重する「礼儀」である
「礼儀」ほど心温まるものはない。「礼儀」はあいさつに始まりあいさつに終わる。
あいさつは礼式ではあるが、一生に一度のチャ ンスをいただいたという茶道の「一期一会」の
心の姿勢が望ましい。
(2)職場にあって取り交されるヤル気の合図である
仕事の上での行動にも、ケジメが なくてはならない。1 日を通じてのあいさつは、職場仲間の
合図となって、リ ズムとスピードと活力を生み出すものです。
(3)明るい人間関係をつくり出すものである
さわやかなあいさつと言葉遣いは 、清新な気風を吹き込み、明るく和やかな人間関係をつくり
出す。
この オアシスづくりを忘れてはならない。
人の心と心を結ぶかけ橋は、あいさつによってつくられる。
2.接客の基本姿勢は、最敬礼と微笑に尽きる
あいさつの仕方、名刺の出し方、座り方、言葉遣い、手の 位置、足のあり方等々
これらに共通する精神は“ お客様を敬う”ということです。
その基本姿勢は最敬礼と微笑に尽きる。言語と態度は正比例する。
このような姿勢を取る時には、ゾンザイな言葉は出てこない。
また、それ にそぐわないような動作をするわけにはいかない。
ある菓子製造販売のA社ではウィークデーの早朝というのに、お客様の列が引きも切らない。
名誉総裁高松宮賞受賞の菓子のうま さもさることながら、 店長以下、社員・パートさんのあい
さつ・応対は、ともかく見ていて気持ちがよいを通り越して感動を覚える。
にこやかな笑顔で「おは ようございます。いらっしゃいませ」「はい」「かしこまりました、少々
お待ちくださいませ」「こちらでよろしいでしょうか?」「おつかいものでしょうか?」等々。
お客様が言う前に、実にタイミング 良く聞いてくる。
最後に「ありがとうございました。またどうぞお越しくだ さいませ」と笑顔と最敬礼で締めくくる。
リズムとスピード感が何とも言えない。見ていると当たり前のことばかりであるが、徹底した
誠実さがフレッシュな感じを与えているのです。
よく「答えはお客様が出す。お客様に聞いてみなさい」というが、A社では基本を忠実に実行して
いるわけです。
3.あいさつのチェックポイント(真心を行動に移しているか)
(1)気配りは
① 相手より先に声を出そうとしているか
② 親しみがこもっているか
③ 応答のあいさつの タイミングに合わせているか
④ 謙虚さが態度に示されているか
(2)正しい表現は
① あいさつ、言葉に表情と 動作がともなっているか
② 表現に明るさ・元気の良さが見られるか
③ 正しい姿勢を取っているか
④ 正しい言葉遣いを しているか(お客様、上司)
(3)習慣づけは
① 日によってあいさ つの仕方にムラはないか
② 特定の人だけへの あいさつになっていないか
③ ごく自然なあいさつが交わされているか
4.あいさつの徹底・励行のためには
(1)先輩、上司が「率先実行」する
(2)あいさつをしない人には、 こちらから先にあいさつをしてみせる
(3)間違ったあいさつ、言葉遣いなど は、気がついた人が、 だれでもその場で注意する
(4)電話のかけ方に も「あいさつの型」をつくる
(5)「あいさつ」「かけ声」の強化月間を3ヵ月に1 回程度設けて全社運動を展開し、
“良い返事もあ いさつの一つ”と心がけよう
大きな声で元気よく 「ハイ!」が出るように(「ハア」や「ハイハイ」などは三流)。
「ハイ」の返事と同時に、呼んだ相手の方へ顔を向ける、また は素早くそこへ向かって動く。
あいさつに続く次の言葉を、相手を見て付け加えていこう。
特に、別れる時のあいさつには一言添えよう。
「別れの言葉は次の出会い の第一歩である」。
微笑を添えたあいさ つは、心が数倍に伝わっていく。「微笑は美粧にまさる」。
最敬礼のできる人間になろう。「最敬礼のできる者には、礼儀の心が宿る」。
人間関係を良好に保ち、結果的には良い仕事を成し遂げて社会の役に立つ。
その第一歩があいさつです。
「あいさつは基本動作のはじまり」の リズムづくりを、全社的に展開していただきたい。
<チェックポイント>
1. あいさつは基本動作のはじまり
2. あいさつは明るい人間関係をつくる
3. 先輩・上司が率先実行せよ
□電話は心の応対・電話は生きた情報・速く明確に丁寧に
1.基本的心構え
(1)声で伝える会社の心
電話は、会社を代表する「声」 であり「言葉」です。
声には「心」があり、言葉には「意思」がある。
その応対の善し悪しが、会社のイメージを変え、会社の信用と業績を決する。
(2)タイミングとスピードが命
必要な時に素早く、簡潔に用件を伝えることが、ビジ ネスを成功させ会社を発展へと導く。
企業活動は生きた情報の流れ、実際に伝える活動がうまくいくかどうかで、その運命が
決まってしまう。
(3)私用電話は公私混同のはじまり
私用電話は、職場の離脱行為で あり、会社への背任行為です。
仕事のリズムを狂わせ能率を落とし、電話回線を中断して、得意先に多大な迷惑をかける。
2.応対の原則
(1)受話器は正しく持つ
左利きでない限り、受話器は左手でとるのが基本。
送話口から握りこぶし一つ程度あけて口に近づけ、姿勢を正す。
同時に、右手にはメモとエンピツ(筆記用具)を欠かしてはならない。
(2)正しい言葉、ハ ッキリした発音、明確な語尾
電話応対は相手の顔が見えないだけに、言葉遣いにはかなり気を配らなければならない。
発音のまぎらわしいもの「美容院・病院」「私立・市立」などの同音異義語の場合は字解をする。
日時の場合も「何月何日の何曜日、午前○○時」という言い方をする。
「あります」「ありません」は「す」「せん」で反対の意味になる──など語尾を明確にしな
ければならない。
話し言葉は「ございます」調が良い。
一般に電話応対は「丁寧すぎるかな?」と思うぐらいで丁度良い。
<声の明確化5原則>
①正しい言葉で話す
②ハッキリ発音する
③声の調子を弾ませる
④適度な速さで話す
⑤語尾をしっかり発音する
(3)社内には敬語をつかわない
社外の人に対しては、たとえ自分の上司であっても「 ○○は・・・」あるいは「課長の○○は
・・・」と呼び捨てでよい。
(4)適度な速さ、低めの声量
早口は聞き取りにくく、大声も周りに迷惑です。
電話器は約4メートル四方の音声をそのまま伝えるので、電話を取り次いだり、通話の途中で
打ち合わせをする時は、必ず保留ボ タンを押すか送話口を手で押さえること。
(5)誠意、親切、丁寧
電話で話しながら、盛んに頭を下げる人をよく冷笑する人がいるが、それは電話の怖さを
知らない人です。
声の調子というものは、身体の調子や病気、あるいは姿勢によって大きく左右されます。
機械は正直で、思っている以上にこちらの状況を先方に伝えるものです。
相手に敬意を持ち、誠意のある応対が必要。
また、電話中の人に連絡が入った場合「○○は電話中です」だけでは不親切です。
「お待ちになりますか、それともこ ちらからおかけいたしましょうか」と聞くべきです。
3.電話のかけ方、受け方
(1)電話をかける前(準備)
①相手の番号、所属、役職名、氏名をよく確認する。
自分がよくかける相手の電話番号は、すぐ分かるように自分用の電話番号一覧表を作って
おくとよいでしょう
② 用件を5W2Hに整理し、話す順序を簡潔にメモしておく
③ 必要な書類、資料などを手元に置いておく
④ すぐにメモ が取れる状態にしておく
⑤ 長距離電話は、通話料が高い 。
メールやファクシミリで済ませられないかを検討する
(2)電話のかけ方
協業のご案内
メルマガ登録(無料)はこちら
お問合せ・ご質問はこちら
組織人としての基本動作とは
■報告・連絡・相談
1.指示命令・報告・連絡・相談のスピード循環が仕事の成果を決める
企業の業績は突飛なところから出るの ではなく、社員一人ひ とりの日常の実践結果から出る。
作業+心(知恵)=仕事 仕事とは成果、顧客満足、増客、好感度企業イメージにつながるもので
なければならない。
あなたの会社の社員は仕事をしていますか?
作業に心と知恵を付加するには企業組織の土台となる部分に経営理念と年度経営方針が明確に表記
され、一人ひとりの社員の行動につながるように具体化(行動言語化)されていなければならない。
指示命令とは仕事の成果を決める第一歩であり、部下に成功体験を積ませてやるリーダーシップ
発揮の重要な基本動作です。
その事を幹部は理解して、指示命令を出さねばならない。
相手のレベルにあわせて、その仕事のポイン ト(何が大事か)をわかりやすく5W2Hで説明し、
本当にわ かってくれたかを復唱でもって確認しなければならない。
期限などの曖昧な指示は非効率な仕事を生み出す元凶です。
従って、指示命令をうける社員は、ハイの返事、左手にメモ、駆け足の3拍子で上司の前にいき、
指示をうけ、復唱をすることが、ミスのない仕事をする必須条件です。
報告連絡は仕事のけじめであり、潤滑油であり、能力を高める場であることを新人からベテランに
至るまで徹底することが 重要。
そのことが仕事のミスを防ぎ、顧客満足を高め、業績アップにつながるということを仕事を通して
知らしめていく(O.J.T=オン・ ザ・ジョブ・トレーニング)。
報告と連絡の違いがわかりますか。
社員に聞いていただきたい。
連絡とはあるがままの事実を正しく速く上司に伝えること:「部長、最近A社の社長、経理部長が
留守がちです。今日は白塗りの外車にのったおかしな人間がきてました」
報告とは自己の判断を加えて、上司に進言すること:「あれはひょっとしたらマチキン(高利の
金貸し屋)ではありませんか? 一度法務局で不動産に対する担保の移動状況など調べてみたら
どうですか。在庫も多いようだし、資金繰りが逼迫しているのでは?」
このように日々の報告を通じて、自己の判断力を上司に近づけていくのです。
こうして意味を理解させ、反復実践をさせ、体質化すると、企業は環境変化に鋭敏な感度をもった
強い組織になっていくのです。
さらに相談という基本動作は、仕事を進めるうえで判断に迷ったり、分からないことに遭遇した
時に上司、指示者に素直な気持ちで教えを請うことであり、これも良い仕事をする基本動作です。
知ったかぶりや、曖昧なままでの仕事は必ずピンぼけの結果につながるものです。
従って、相談をかねた中間報告をタイムリーにする社員ほど上司から信頼されるといえます。
企業の目的である存続・発展のために、情報管理は重要な役割をもつ。
今わが社、自部門に何が起きているのか、お得意先は、ライバルは、そして部下は……。
これら諸々の情報をいかに速く、正確にキャッチし、適切な処置をとるかが幹部の使命といえます。
社員⇔幹部、幹部⇔社長、また社員⇔ 社員、幹部⇔幹部と縦横無尽に報告・連絡・相談が飛びかう
会社に沈滞ムードはない 。
社内活性化の決め手は報・連・相にあるといっても過言ではない。
2.トップ・幹部の姿勢
報・連・相を根付かせるポイントは、トップ・幹部のあくなき追求姿勢にあります。
放任では良き報・連・相のリズムは生まれ ない。
トップ・幹部の厳しく、忍耐強いホーレンソー(報・連・相)質作り(ホーレンソーを食べて
組織パワーアップの意)の実践行動が欠かせない。
<事例1>
地場の中小工務店A社(従業員20人)は創業10年で年間50棟くらいの実績をあげていたが、
着工戸数の減少傾向下、いかに受注率をあげ、取りこぼしをなくすか、クロージングを速く、
確実にやりきるかがテーマであった。
営業会議では5人の営業担当がそれぞ れの見込み客をカルテ化し、営業重点を明確にしていた。
しかしながら各人の行動に はバラツキが多く、予定通りいかないことが多く発生していた。
そこで担当者のPD CA(プラン、ドゥー 、チェック、アクション)を確実にまわさせると
ともにトップ 、幹部のCAHF(チェック、アドバイス、ヘルプ、フォロー)をタイムリーに
実施、成約率をたかめるためPDCA・CAHF連動作戦を展開して、 成約率アップを図った。
左右2欄に予定と実績を書ける日報をつくり、担当者は夕方帰社時に本日の訪問実績を右側に
記入。
翌日の本日の予定欄に明日の訪問予定を書いてトップに提出。
朝は朝礼で再度、予定を確認。
トップ、部門長のアドバイスをうけて、営業に出かけ、携帯でただ今より○○様ご自宅に入り
ますと連絡。
商談を終えて 出るときに終了報告を携帯で入れる。
会社に入っている他の連絡情報を本人に伝える。
最初はそこまで拘束されたらかなわないという印象をもっていた営業担当も顧客、営業、会社間
のコミュニケーションがよくなり、顧客評価もあがるにつれて、この仕組みも当たり前になり、
全員の体質となって全社にクイックレスポンス、クイックアクションのリズムができあがりその
結果、顧客満足、成約率アップにつながっていた。
<事例2>
B社は地域を代表する、というより業界改革のリーダーシッ プをとっている不動産仲介業者です。
顧客が顧客を呼ぶ善循環企業体質をつくるため、「CS経営の推進で安定業績基盤を創造」を
年度スローガンに掲げ企業体質強化に取り組んでいる。
そこで顧客満足の向上のため、挨拶、朝礼、指示命令、報告連絡相談、クレーム処理など基本
動作の本質を徹底究明し、社員の行動言語(書かれた方針の具体的行動対策)にまで落とし込む
作業を繰りかえさせ、経営方針行動マニュアルとして成文化している。
CSといえばクレーム対策ということになるが、B社のクレーム処理マニュアルには以下のように
規定され、実践されている。
(1)クレーム処理は特急処理、いかなる業務より最優先。
人間のすることだからたまにはミスや失敗もある。
問題は「ピンチの後のチャンス」であり、全身全霊、最優先で対処する
(2)小さなクレームほど天の声として大事にし、即、社長に文書で報告。
不在時は次席の者に必ず報告する
(3)クレームを発生させた者の責任は追及しないが、報告しなかった者は組織人としての
基本を欠くとして始末書を書いてもらう
(4)同じクレームを2度起こした者は1回目の教訓がいかされていない不誠実者として
罰則の対象となる
(5)重大クレー ムは社長が率先担当する
(6)クレーム処理がすんだら社長に処理結果と再発防止策を報告し、マニュアルにいれる
(7)クレーム処理後は相手先への訪問件数を3ヶ月間倍増し、クレーム客から紹介客に
なってもらう
特に(3)や(7)はトップ の想いが入り、秀逸です。
3.多面的な報・連・相の手段
口頭や書類を問わず目的を共有化し、業績を上げてゆくために指示命令報告連絡はビジネスの基本
サイクルであり、漏れのないよう「ダブっても報告、スピーディに連絡、素直な心で相談」が基本
であり多面的に展開すべきです。
(1)口頭・朝終礼・会議・定時電話連絡・顔を合わせたとき・その他
(2)携帯電話、パソコンメール 活用、社内LAN、グループウエア活用
(3)書類・報告書・ 始末書・レポート・メモ・その他
財務会計視点からの基幹系のIT化から、受注見込み情報の共有化と全社対応、知恵の共有化の
ためグループウエアを導入する企業が増えている。
拠点、部門別に会議室データベースをもうけて、部門長がメンバー個々人へデータベースを通じて
指示を出すと、他のメンバーも同時に共有化でき、判断基準の統一につなげることができる。
4.チェックポイント
(1)放任では良き報・連・相のリズムは生まれない
(2)督促とタイ ムリーな応答が不可欠
(3)指示者に聞かれたら負け、聞かれる前に報告が基本
□会議
急成長を続ける会社では、常に社員がフル稼働で、一堂に会する機会も少ないものです。
そして新しい社員が次々仲間に加わってくるため、社長の経営思想、ビジョン、方針を浸透させ
にくい。
またいろいろな決定事項を末端まで徹底しにくいものです。
<事例>
一見、過剰と思われるくらいのキメ細かさで特に
①意思統一
②方針徹底
③人財育成
という三大目的で会議制度を設けている、急成長中の企業の事例に学ぶ。
1.会議の種類
2.会議の準備
(1)共通準備
①運営スケジュール表(進行予定表)のパネル掲示(※ 司会者はこのパネルの運営項目の
スケジュールに従って、会議の進行を進めて行く)
②プロジェクター
③当月報告書綴り(検討資料として一冊に綴じたもの)
④マジック3色(黒、赤、青)
⑤研修用視聴覚教材( ※会議の種類、内容に合わせて使用)
(2)参加者個人の準備物
①議事録ファイル(前回決定事項チェックのため)
②手帳、筆記具、ノート類、電卓など
③報告、検討に必要な関係資料・書類
3.運営のポイント
特に核になる「経営会議」の運営内容を中心に紹介します。
(1)会議室には、事前に前記準備物を一式揃えておく。
(2)運営項目(※司会者・ 議事録担当者は輪番で決めておく)
4.よくある会議の問題点と対策
(1)“うちの会杜は会議が多くて困る”
どの会社でも、意味なく多くの会議を行っているところはないのであるから、なぜ多いか
(その必要性)について考えねばならない。
A.急成長中で、思想集団としての意思統一と結束強化が必要
B.決定事項の徹底とチェック(やっていかねばならないことが沢山ある)
※人材レベルのアップによる組織体制の成長とともに、会議の種類、頻度も見直しが必要になってくる。
(2)“うちの会議は長くて疲れる”なぜ長引くのか?
参加者の問題意識が低く、意見があまり出ない。従って、司会者一人がいらいらしてあせり、
「どうですか?どうですか?」 になり「何か意見はありませんか?ありませんか?」ついには
「進行できませんので何か言ってください」式にやっているので長引く。
会議とは自分たちの問題を、自分たちの力で知恵を出し合って解決するために会して議し、
議して決し 、決して行っていくものです。
(3)“決めたことが実行されていない”
A.何を決めたかの確認がはっきりできておらず、それの 意思徹底に欠けるから実行されない。
B.決定事項は議事録を即日作成、参加者回覧また は参加者全員へ配布。
C.特に、実行度合いを関係幹部が中間チェックすることがポイントである。
(4)“会議の内容が薄い”
準備不足で急に会議に出席すると、思いつきの意見は出せても、じっくり練った意見は出せない
ものです。
会議前には 部門内、または部門間で意見調整を済ませておくべきです。
各種関係資料の分析、準備をしておき、常に自分の判断(意見)を持っていなければならない。
――常に成果は準備力に比例する――のです。
5.早朝会議の実施
トリンプやキヤノン、ワタミフードサービスなどトップの理念、方針が明確で業績好調な会社は
早朝を利用した会議を継続的に実施し、即断即決、即日実行のクイックレスポンス、クイック
アクション体制を確立している。
(1)朝なら会議に参加しやすい
(2)疲労のない顔つき、状態で会議ができ能率もあがる
(3)決定事項を即現場に落とし込む行動が展開できる。
クイックレスポンス、クイックアクションのリズムがつくれる
早朝会議を成功させるには
(1)トップが出席、即決即断の体制をつくる
(2)トップがでてもフラン クに話し合える雰囲気がないとダメ
(3)当日、決めねばならないことを決め、即日断行
(4)何故、そうするかの判断能力を鍛える場にする
などが必要となります。
メルマガ登録(無料)はこちら
お問合せ・ご質問はこちら
組織人としての基本動作とは
■ビジネスの成否は「話し方」が決める
仕事を成功に導くために欠かせないことが、2つあります。
まず、目標設定、企画、戦略、戦術などの「仕事の中身」。
次は、それを実現するための会社・萬故・指示・連書・報告・相鼓などの「仕手の進め方」。
その仕事の進め方の2大手法が、言うまでもなく「書く」と「話す」です。
それも、使う頻度や要する時間などを考えれば、圧倒的に「話す」機会が多いはず。
まさしくビジネスの成否は「話し方」が握っているといえるでしょう。
ところが、それは十分に分かっているのに実行できないケースも多いのも事実です。
2つの理由がありそうです。
1つは、上達のためにとくに重要な課題が分かっていないこと。
2つは、課題をクリアするポイントに気づかないこと。
□上達の7つの基本
話し方の成否を決める最大の要素は、やはり「声」と「言葉」でしょう。
それぞれを上達に導くポイントは次の7つです。
1.発声
とくに発声では、大きな声、よく通る声で、口ごもらずはっきりと発音をしましょう。
それには(声そのものでなく)声帯の振動によって声を創り出すことを意識するのがコツです。
2.姿勢
よい発声をする秘訣は、肩の力を抜き、背筋を伸ばした楽な姿勢で、まっすぐに前を向き、
首とあごの角度を直角にして話しましょう。
3.テンポと間
情報を容量よく伝えたいときにはアップ・テンポで、相手を安心させて情感に訴えたい
ときにはスロー・テンポで話すのがコツ。
間合いが短い話し方は聞き手に気ぜわしく感じさせ、長過ぎると退屈になります。
ほどほどの間合いを保ち、ときには意図的に間合いを設けたり省略したりのメリハリを
つけるのがベストです。
4.抑揚
平板な話し方は相手が退屈する上に、印象に残りません。
声に抑揚をつけることで話にリズムを持たせたいものです。
5.言葉選び
短くてインパクトの強い言葉を選ぶこと。
通常のスピーチでは同じ言葉の繰り返しを避けて変化を持たせる方法がベターですが、
逆に、もっとも訴えたいキーワードを繰り返すという手法もあります。
6.組み立て
原稿などを準備する段階で話の「起・承・転・結」を準備しておくこと。
ときには衝撃的な結論を最初に紹介する「結・起・承・転」も効果的です。
7.短く話す
どんなに中身がよい話も、長過ぎては反感を買うだけ。
時間はできるだけ短く、中身も枝葉の部分はカットして大切なことだけを伝えるようにしましょう。
□上手な話し方 5つのポイント
以上の基本を守れば「聞きやすい話」はできますが、「聞き手の心を惹きつける話」が
できるとはかぎりません。
とくに商談、説明会でのプレゼンテーション、会議での発言、会合でのあいさつなどの場では、
さらに以下の5つのポイントに気をつけたいものです。
1.体を駆使する
立って話す場合は「姿勢」を正しく。
大切な場面では聞き手の「目」を注視するなどのアイ・コンタクトを大切に。
笑顔(とくに口元に笑みを)で聞き手に安心感と好印象を与えるのも効果的。
両手を動かすなどのアクションを交える……などでインパクトが増します。
2.つかみ・さわり・おち
話を、つかみ(開き手を本題に導くための話題)、さわり(本題)、おち(話の
しめくくり・印象的なシメの言葉)で組み立てるのが基本。
3.会話のネタを探す
「つかみ」でとくに大切なのが、商談などで双方の気持ちをほぐすための話題選び。
よく言われる 「木戸に立てかけし衣食住」という11文字のノウハウがあるように、
以下の11項目が代表のようです。
キ=季節・気候
ド=道楽・趣味
ニ=ニュース
タ=旅
テ=テレビ
カ=家族
ケ=健康
シ=仕事・業界・社員
衣=ファッション
食=食べ物・グルメ
住=住居・故郷
4.敬語力
話に中身はあっても、目上の相手に対する敬語が上手く使えなくて失敗するケースはよくあります。
得意先に対して「ご苦労さま」(正しくは、「お疲れさま」)などはタブー。
本や雑誌で正しい敬語をマスターしておくべきでしょう。
5.楽しい会話の演出を心がける
同じ話を聞いても、不満や不愉快に思うことと、楽しく気持ちよく感じたりすることがありませんか。
その差を生む大きな原因は「相手へのホスピタリティ」の有無。
仕事でも、次のように頼み方ひとつで部下のやる気は変わってくるでしょう。
×……「おい、やってくれ!」と命令調で部下に指令を出す。
○……「忙しいのに悪いけれど、やってくれないか?」と頼む。
職場の飲み会で上司が説教や自慢話ばかりをするのも同じ。
極力、聞き役に回って部下の話や本音を聞く努力も大切です。
□場面別の会話術-11の代表例
仕事の中身によって違いますが、頻度が多く、重要度が高く、しかも難しいの
が次の11のシーン。
それぞれのもっとも大切な点を列挙してみました。
1.電話
話すべき要点を整理しておき、必要ならば手元にメモなどを準備しておくと要領よく話せます。
電話口では、明るく、ハキハキと、元気な声を出すように。
2.指示・依頼
頼み事は、威圧的でなく、低姿勢で、具体的に依頼したいものです。
×……「急いで返事をくれ!」
○……「明日の午前中までにメールでいただけませんか?」
3.報告・連絡・相談
仕事に欠かせない「ほうれんそう」でもっとも大切なのは、早めに、こまめに、正確に、素直に
行うこと。
とくにミスや事故の場合はおろそかになりがちなので、要注意です。
4.商談
前出の7つの基本・5つのポイントに加え、大切なのが「時間管理」。
忙しい先方のためにも、要領よく、短時間でまとめるのがコツ。
そのためには、ムダ話を避けて集中すること。
話を補足する資料などの準備も大切です。
5.会議
7つの基本・5つのポイントがもっとも活きる場。
ただし、忘れてはならないのが時間管理です。
自分一人が話し過ぎないように注意し、発言が長くならないように話す内容を刈り込んでおく、
などの配慮が大切です。
6.プレゼンテーション
5と同様ですが、気をつけたいのが資料やパワーポイントに頼り過ぎないことです。
資料が多くなり過ぎると、話が散漫になり、聞き手の印象が薄れるだけ。
あくまでも主役は「自分の言葉」なのです。
7.発表、講義、セミナー
会議や発表会での報告、研修での講義などでは、話の租み立ての準備を怠らないこと。原稿の
棒読みは 避け、単調にならないように、話す速度と声の大きさにメリハリをつけます。
聞き手の顔をしっかりと見て、少人数では歯切れよく速めに、大人数では大きめの声でゆっくりめに
話すのがベター。
8.怒る・褒める
怒るときは、相手だけを前にして、小さな声で、冷静に話すこと。
褒めるときは、大勢の前で、大きな声で、感情をこめて話すことです。
9.クレーム対応
迅速に対応し、適切なタイミングで謝ること。
反論があっても先方が怒っているのは事実である以上、真摯に言い分を聞くこと。
また、「とにかく謝っておけばいいんだ」という態度でなく、心から謝罪し、リカバリー策を示す
努力が大切です。
10.朝礼のあいさつ、スピーチ
どちらも 「短時間、1テーマ、1キーワード」が秘訣。
目安は3分以内。
話すべき中身を1テーマに放り込み、言葉も平板にならないように、話のなかに「印象に残る
キーワード」を盛り込むのが秘訣です。
11.接待、会食、パーティ
接待や取引先との会食ではお客さまの話を引き出す役目に撤し、笑顔の出る楽しい話題を心がけたい
ものです。
パーティでは、同じ部署や知り合いだけで話さずに、初対面の人にも気軽に声をかけることで人脈が
広がります。
□相手別の会話術-5つの代表例
話す相手が変われば、話す中身や者し方も変わります。
仕事の場でとくに気をつけたい5つのケースについて考えてみましょう。
1.上司・部下
上司に対しては、遠慮せず懐に飛び込むこと。
また、忙しい上司には「今、よろしいでしょうか?」と確かめたり、話す内容をよく整理しておく
ことです。
部下に対しては上に立つ人から「あいさつ」などの声掛けをするのがベター。
その際も、威張らず、押しつけず、がポイントです。
また、世代差や意鼓・生活のギャップに気を配り、相手の立場に合わせる努力も大切ですが、
無理して迎合するのも問題でしょう。
2.取引先
ビジネスである以上、必要なことはしっかりと主張。
しかし、あくまでも相手の立場を尊重し、攻めると同時に引き際も大切にするのが成功の秘訣です。
3.初対面の相手
最大の課題は「相手はどんな人物だろうか?」というお互いの不安を取り除くこと。
笑顔と丁重な言葉遣いはその第一歩です。
また最初は、軽い雑談や世間話を通じて相手の人柄や性格などをチェックするのも一法です。
4.コミュニケーションが苦手な相手
最近では若い人を中心に、他人とコミュニケーションを取るのが苦手という人も少なくありません。
こちらから話しかけたり、答えやすい話題を投げかけたり、といった方法で、相手の心をほぐして
いきたいものです。
5.家族との会話
本来は大切なのに、意外に無視されているのが家族との会話かもしれません。
「疲れているから」や「面倒だから」と話さない人も少なくないようです。
しかし、コミュニケーションの第一歩は、まず話してみることから。
もっとも近しい立身の家族と上手く話せないようでは、価値観や立場の違う者同士が集まる仕事の
場での会話が成功する道理はありません。
□「会話力」を磨く決め手とは
会話カを磨くためには、ノウハウを覚えるだけでなく、ふだんの心がけも大切です。
その奥義は、次の5つに尽きるでしょう。
1.言葉のストック
上手な会話の決め手は、やはり開き手の心に響くインパクトのある言葉に尽きます。
そのために必要なのが、日頃から言葉のストックを増やす努力。
本などで読んだ名文や名文句、講演やスピーチで心に書いたキーワードなどがあれば、
手帳などにメモしておくのもよいでしょう。
2.話題の引き出し
商談のつかみや相手と打ち解けるための雑談で威力を発揮するのが、斬新な話題。
そのためにも本、雑誌、テレビ、インターネットなどのメディアや、人から聞いた面白い話などの
多種多様な情報を集めておきたいものです。
3.ユーモア
相手の心をひらき、その場を打ち解けさせるのに効果的なのがスピーチや会話でのユーモアです。
秘訣は、心をひらいて、明るく接し、場を楽しく演出しようという気持ちを大切にすること。
その意味では、若手社員などからひんしゅくを買うダジャレや親父ギャグも立派な会話の小道具
かもしれません。
4.「話す」より「話させる」
「話し上手」は「聞き上手」と言われるように、話好きな相手との会話の場では、「自分が話す」
よりも「相手に話させるほうが有効。
また、こちらから適切な質問や問い掛けをする「聞き出し上手」になるのもよいでしょう。
5.現場を踏む
そうした『会話の達人』になるには年季も必要。
日頃から一人でも多くの人と、少しでも多くの場で話し、聞く機会を持つことが上達の第一歩
でしょう。
「習うよりなれろ」という格言がありますが、上手な話し方にこそふさわしい教えかもしれません。
メルマガ登録(無料)はこちら
お問合せ・ご質問はこちら
組織人としての基本動作とは
精一杯で、それ以外のことはあまり記憶に残らないというのが実情です。
やすいです。
教育を進めていくためには、まず入社数ヵ月後の新人たちがどんな状況にあるかを把握しておく
ことが必要です。
まず確認します。
分けると次の5つの内容になります。
日常は満足すべきものかどうか、仕事に埋没することなく、きちんと問題意識をもっているか
どうか。
前で講義することに
よって、自分の担当している業務や商品についての理解を深め役立たせる。
励ましを与えてもいます。
企業の運命を左右するとまでいわれています。
A社は、市内を中心に5店舗(ヘアサロン4店舗、エステティックサロン1店舗)を有するビュー
ティーサロングループで構成されています。
目標に対して業績数字の検討に始まり、問題点の摘出と改善策まで。
飛び交う。
女性だけの職場においては、一人ひとりが持てる力を十分に発揮し、活かされ、活きている。
いて、戦力化・活性化とはほど遠いのが実情です。
これらは、当の女子社員自身の問題以前に女子社員を取り巻く環境にあるといえましょう。
いくことができれば、期待以上に仕事の生産性はあがるはずです。
紹介します。
中途半端に終わってしまいます。
企業=経営者が分かる)。
実施する。
発表させる
(後のチェックフォロー必要)
させることです。
植え付ける。
お問合せ・ご質問はこちら
組織人としての基本動作とは
■「接客」と「接遇」
ビジネスの世界では、お客様に接する役割をもつ応接者、お客様をもてなす処遇者などを総称して
「接遇者」と呼んでいます。
お客様を遇することに努力している会社、官公庁などの集団では、「接遇」ということばが浸透して
います。
ところが、最近このことばを知らない人がいることにたいへんな驚きを感じています。
昔は、お客様を遇することを応対、応接、処遇などと言っていて、その場限りのもてなしで終わっていた
のです。
しかし近年では、経済活動の場は当然、官公庁などでも、お客様の満足度の重要性が一段と認識されて
きました。
お客様に接することを、もっと深く、長期的な顧客関係を築く上での大事なきっかけと考えるようになり
ました。
そのため、日常的に「接遇訓練」が研修の中心にすえられ、極めて広範囲になされています。
ところで接遇の方式は、どうしたらお客様に満足していただけるか、という心構えや、それが表現される
形が、最も一般的な尺度として定着したものと考えてよいでしょう。
もっと広い意味では、周りの人と仲よくしていく社会的な態度能力と考えてもよいと思います。
つまり現代を生きる社会人としての必須の教養なのです。
□「接遇」は自身の人間力
さて、現代の組織活動は、窓口を中心にして動いている、と言われています。
内と外を結ぶ接点にいるのが接遇者です。
その善し悪しが、組織活動の成功不成功に大きな影饗を与えます。
そのような意味で、お客様と接する立場にある人の責任は極めて重大です。
ところで、接遇の目的は、「最良のサービスをして、お客様に最大の満足をしてもらう」ことですが、
サービスの方法にはいろいろあります。
食事にさそう、宴会を設けて酒を一献くみ交わすなど、物質的なもてなしをする方法もありましょう。
物を売るとき値引きをする、ということもあります。
また、それよりも基礎的なこと、一般的なことで解決しなければならない重要なことがたくさん
あります。
このような物質的・機能的・金融的なもの以外に、細かい心づかいで、献身的な協力で、温かいことば
で、明るい表情で……など、本来の“心を豊かにする”接遇の条件を総合的に考える必要があります。
しかし究極的には、接遇に生命を与え、血を通わせるものは、技術を超えて、徹する心であり、あなた
自身の人間力なのです。
しかし、よくしようという気持ちさえあれば、すべてことがうまくいくかというと、必ずしもそういかな
いところに接遇のむずかしさがあります。
悲しいかな人間は完璧ではないからです。
また、お客様はある種の環境の中でそれぞれの行動のパターンに慣らされていますので、その基準をもと
にして、最初から「こんなときには、こうすべきだ」といった要求をあなたにつきつけているからです。
その期待に添わない、突飛な態度やことばづかいでは、それだけで違和感をもたせてしまいます。
形式もまた、見すごせない大事な接遇の要件なのです。
さらに、現実のお客様とのかかわりはほとんど束の間の対峙で終わります。
だから、相手に快い感じをもたせ、自分のよさを認めてもらう、そして相手への思いやりを正しく表わ
す、いい意味での「演出」が必要なのです。
形を整え、相手に不愉快な思いをさせない努力をすることもその人の心くばりなのです。
すばらしい接遇は、組織目的の成功不成功だけでなく、周りの人の心を豊かにしてくれます。
一回一回の接客はささやかかもしれませんが、その波紋は大きなうねりのようになって社会全体に拡がっ
ていくことになります。
大げさに聞こえるかもしれませんが、そのような意味で人をよりよく遇する人は、平和の使者みたいなも
のだと言っていいでしょう。
□あいさつに始まりあいさつで終わる
私たちの接しているお客様は、機械や品物と違い、「人間」という、感情をもった動物なのです。
そのお客様にどのようにして親しみをもってもらうかということは、接遇者の大事な目標の一つです。
ところで接客の基本的な心は、必ず表情や態度、ことばづかいになって表われるものです。
だからといって、心さえよければどんな態度でもよいということにはなりません。
自己流の突飛な態度やことばづかいでは、お客様の目や耳になじみません。
接遇も基本的には、他者との人間関係をどう解決するかということですから、今まで述べたことばづか
い、態度、表情、身だしなみなどすべてがかかわってくるのです。
次に、お客様と出会ったとき、よい人間関係をつくるために、具体的にはどうしたらよいか考えてみよう
と思います。
人は会い、人は別れ、そして人はまた出会うのです。
人生とはそのような意味での人と人との出会いの連続であるとも言えます。
そのときどきにふさわしい一言が、相手と自分とを結びつける連結器や粘着剤になるのです。
あなたが現在もっている交友関係でも、最初出会ったときのあいさつから始まっているはずです。
もし、そのとき、声をかけなかったら、ただ行きずりの人でしかなかったはずです。
そのような意味で、出会いは急に始まり努力によって実るのです。
人が社会人としての資格をもっているかどうかを最初に問われるのが、極めて簡単なこのあいさつです。
あいさつということばはいろいろな意味をもっています。
ひと言あいさつするのを無精したために近所づき合いが悪くなったり、大事なお客様との人間関係を
こわしている人は案外多いのではないでしょうか。
これからは、さっそくだれとでも明るく積極的なあいさつを交わすようにしましょう。
□人間関係のきっかけになるあいさつ
1.あいさつは先手で
人間関係はつくられるものではなく、積極的に自分からつくるものです。
“あいさつは先手で”ということです。
多くの人が、相手に先手を打たれて、気まずい思いをしたことがあるはずです。
接遇者はお客様との人間関係づくりに人よりも何倍も力を注ぐべき立身にあるのだ、と自覚しなければ
なりません。
前に待たせたことのあるお客様には、「先日はたいへんお待たせいたしました」と言えば、お客様も
「どういたしまして」となるでしょう。
先手は強いものです。
「雨もあがりましたね」「そうですね」―このような他愛のないことばをかけ合うことが大事なので
す。
それは相手に対して無視していないことを示している証だからです。
「どちらまで」「ええ、ちょっとそこまで」「ああ、そうですか。じゃあ行っていらっしゃい」と
いった会話がなされます。
この場合、行き先がわからなくてもかまいません。
あいさつ自体が大事なのです。声をかけないと相手は無視されたと思います。
人間は、自分を中心に考える動物だ、とよく言われます。
集団写真を見るとき、多くの人はまず自分を探します。
この自己中心的な気持ちが、私を無視しないでほしいという、他人に対する要求になって表われる
のです。
「〇〇さん、この前はあの品物で間に合いましたでしょうか」「〇〇様でいらっしゃいますね。お待ち
いたしておりました」
「先だってはご馳走さまでした」など、コーヒー一杯でも菓子折一つでも、ひと言それにふれたあいさ
つをすることです。
こういった、無視しない努力がほんとうのあいさつというものです。
もっと積極的には、温かい関心を示した内容の工夫、しかたの工夫が必要なのです。
ただ、お客様に対してあまり深入りした関心を示しますと、かえって違和感をもたせてしまう場合も
あります。
「いらっしやいませ」「お待たせいたしました」「どうぞ」「少々お待ちくださいませ」など、最初は
慣習的なことばづかいから入るのがよいでしょう。
2.名前を呼び、相互に取り交わす
あいさつは先にと言いましたが、こちらがあいさつをしても相手が返さなければほとんどの人はいやに
なります。
独り相撲に終わってしまうとあいさつは長続きしません。
あいさつは相互に取り交わすものです。
むしろ先にやるようにして、相手が返すようにこちらから仕向けなければなりません。
「竹田さん、おはようございます」「部長、お先に失礼します」「山川さん、また明日ね」とあいさつ
ことばに名前や職名をつけると相手からもことばが返ってきます。
特に、名指しのあいさつをされますと、言われたほうも無視するわけにはいかなくなります。
「真理は単純さの中にある」―このようなだれでもできること、簡単な努力から人間関係のきっかけが
つかめるのです。
特に内部の人とのあいさつが、人に接するときの基礎になりますので、身内で仲よくしていなければ、
お客様がみえたときだけ、急に切り換えて微笑を浮かべ、明るくあいさつをするなどということはでき
ないでしょう。
返事にもいろいろあります。
呼ばれたときの返事、理解を示す返事、了解し、行動する予告としての返事、詫びのための返事など
です。
お客様から声をかけられたとき、それに対して反応を示すのが返事です。
客や周りの人との人間関係を好ましいものにするという面で返事のもつ意味は大きいものです。
「ハイ(拝)の心」が必要だと思うのですが、これは相手を拝む心、おじぎをする心です。
「ハイ」という明るい返事が、後手になった人間関係を逆転させる力になって、積極的に変えてくれる
ものです。
また「配の心」つまり相手に対する細かい配慮としての気くばりを意味します。
返事は、ことばを返す以上に心を返すことでもあります。
好ましい返事とは、次の条件を満たしたもののことです。
・すぐに
・相手を見て
・素直に
・明るく
・心をこめて
また、「ハイ、ハイハイ」などという重ね返事や、大儀そうに答える返事、「ハーイ」というわざと
らしい返事など、ふざけているとか、やる気がないなといった感じを相手にもたせるやり方はさける
べきです。
□接遇の応用問題「苦情の受け方」
初めから苦情をもちこまれないような接遇に努めることが大事ですが、自分の責任でなくても、現実には
いろいろな苦情を処理しなければならないことがあります。
苦情をもちこむこと自体、お客様は大いに問題を感じているわけですから、それに対する対応のしかたに
よっては、「苦情の処理のしかたが悪い」と二重の苦情を引き起こす場合もあります。
苦情処理には一段と細かい気くばりを要します。
苦情をもちこむのは、問題を感じている人のほんの一部でしかありません。
よほどの決心がないと面倒だし黙殺してしまうものです。
むしろ苦情を言ってくださる人は、こちらが気づかなかったり、気づいていてもおろそかにしていたこと
を教えてくださる大事な人ですから、丁重に接するのが当然です。
ところが、多くの人は自分を守るためにすぐカーッとなって、お客様を敵にまわしてしまうことになる
ものです。
どのように対処したらよいかを考えてみましょう。
◎素直に受けとめる
苦情を受けた人でやたらと言い逃れをする人がいます。
相手はその態度に対してまた怒りを爆発させます。
これでは悪循環です。
必要以上に卑屈になる必要もありませんが、相手にご面倒をかけてしまった、という恐縮した態度が
接遇者の誠実さを感じさせるものです。
むしろ素直に詫びたほうが好意をもたれます。
詫びるのは、こちらがすべて間違っているという意味ではありません。
相手に誤解をさせたこと、このようなお手数をかけたことに対して詫びればよいわけです。
相手があきらかに間違っているのであれば、そのあとで冷静になってからおだやかに正せばよいわけ
です。
◎感情的にならない
苦情を受けたとき、喧嘩腰になったらこちらの負けです。
お客様は親切に教えてくださっている情報提供者ではないか、自分の考えを言いはるだけの価値が
あるのだろうか、相手を理解しようともしないで感情的になっているのではないかなど、静かに自分
をふり返ってみることが大事でしょう。
具体的にはゆっくりと、落ちついた声で話してみてはいかがしょうか。
そうするとエキサイトしないですみます。
□苦情の原因を知る
ものごとに正しく対応するためには、そうなった原因をつかむことが先決です。
どうしてこの苦情がもちこまれたのか、その根拠をしっかりつかんで、対応のしかたを誤らないようにし
なければなりません。
初期の段階で失敗しますと解決が長びき、たいへんな労力と時間を要するものです。
それでは問題を悪化させるだけです。
◎苦情をもちこむ心理
いろいろなことが考えられますが、それが正しいか正しくないかはともかく、苦情を言われるにはそれ
なりの原因があるものです。
次のように予想されることがいくつかあります。
・前々から同じようなことがあって我慢できなくなった
・事務的にやられることに対して不満をもっている
・その職場自体に対する悪い先入観がある
・強いプライドからくる自己顕示欲を発散させる
・過剰な客意識からくる怒りをぶつける
・損失の大きさ(経済的、精神的)に対する怒りを我慢できない
◎人が原因か、内容が原因か
どうしてお客様が怒っているのか、それは接客態度について言っているのか、ビジネスの中味が自分の
期待に添わなかったのか、つまり何が間違っているのか、その根拠をはやくつかむことです。
内容が原因であれば、丁重に謝り、損失などを補填すれば、たいがい許してもらえるものですが、人が
原因の場合は、その後に改善してもすでにやってしまったことですから、
納得してもらうことはなかなかむずかしいものです。
予想される原因に次のようなことがあります。
・公平でない。遅くきた人に先に応対した
・丁寧さや親切心がたりない
・遅い、正確でない、間違えている
・態度やことばづかいが悪い
いろいろありますが、こちらも相手と同様に抗弁していると、ますますいきりたってきます。
一旦、受けとめてから、静かに納得してもらうように語りかければよいでしょう。
◎本心をつかむ
間違いを正せばそれでいいのか、態度をあらためろということなのか、相手の望む物と取り換えれば
それだけで解決するのか、よく相手の本心をつかむ必要があります。
「やればいいんでしょう」といった投げやりな態度では、かえって間題の解決を複雑にしてしまいま
す。
相手の本心をつかむというのは、社会的な訓練を経たベテランの人でないとなかなかむずかしいかもし
れませんが、表情、態度、話の内容、語調などから本心をつかむ必要があります。
◎直接話を聴く
苦情は電話で言ってくる場合が多いようです。
目に見えないということ、勝手に会話を終了できるという気安さから、電話での苦情はすぐエキサイト
するものです。
「電話ではなんですから、こちらからすぐ伺います」と直接会って話しますと、案外おだやかに話し合
えるものです。
相手は飛んできてくれたという誠実さを認めてくれます。
□具体的な処理方法
苦情をもちこんだ根拠や、その原因をつかめれば、すぐ間違いなく対応できるかというと、
必ずしもそうではありません。
人間の感情はつねに揺れ動いているものです。
話しているうちに新しい問題がでてくることもあります。
ですから、苦情処理はそのつど新しい問題への対応をせまられる即題の連続です。
一筋縄ではいかないところにむずかしさがあります。
◎相手の要求を満たす
相手の要求を全面的に満たすことができれば、それにこしたことはないでしょう。
物でしたら、新品やサイズの合ったもの、キズのないものと取り替えるとか、人が原因であれば、
だいたい接客態度が中心になりますので、素直に謝ることです。
また、時間的なロス、精神的な苦痛などお客様にかけた迷惑について、それを補償し、心から詫びる
ようにすることです。
理由をタラタラと言ったり、言い逃れにとられるような言い方をしたりすることは厳に慎むべきです。
◎一人だけでは防ぎ切れない
細かい問題や表面的なことであれば、何とか一人で解決できるかもしれません。
しかし、下手をしますと大きく拡がる可能性がありますので、自分だけで悩んでいないで責任のある人
にすぐ報告することです。
苦情は時間がたつとますます悪化する場合があります。
悪化性、重要性をわきまえた処理は接遇者の必須の能力です。
千丈の堤も蟻穴からくずれるのです。
一人でいい子になろうとしたり、細かいことだからここでくいとめられると簡単に考えないでくださ
い。
こうした誤りは案外経験をもっている人の油断が原因になっている場合が多いものです。
◎共同戦線をはる
苦情処理には、責任者を決めて窓口を一本にしぼり、その人を中心にして同僚にも他のセクションの人
にも協力を求める必要があります。
緊急を要する問題もあれば、日時の限られた仕事などもあるからです。
グループが主体の時代です。
職場ぐるみでことにあたらないと、その処理を誤ったために大事な仕事を失ったり、お客様との縁が
いっさい切れてしまったり、ということがあります。
「あの会社はだめだ」とか「不親切な店だ」などという評判を聞くと、人はその評判に左右されやすい
性質をもっているものです。
そのような評判を学者のように分析したり、事実を確かめようとするほど親切で時間的に余裕のある
現代人はいないと心得るべきです。
いろいろな面で言えることですが、口コミはとてもこわいものです。
メルマガ登録(無料)はこちら
お問合せ・ご質問はこちら
組織人としての基本動作とは
| 組織人としての基本動作とは |
| 売ることばかりが先行して重要なことが欠けている企業が少なくありません。 これは企業規模が小さくなればなるほど顕著に現れてきます。 それは何だと思いますか? 基本動作です。
業績向上、人間的魅力創造の不可欠要素と言えるでしょう。 笑顔・明るさのある会社(店)とそうでないところでは、どちらが行きやすいで やらねばならないこと(=基本)を当たり前に実践できることが直接会社の評価・ 私たちの仕事は、やるべきことをやり、やってはいけないことをしないことが重要 当たり前のことを当たり前にやって、初めてお客さまが認めてくれるのが私たち 自社(店)の商売の基本(当たり前のことを当たり前にやる)を再点検してみ “企業体質強化、売上げアップの最大具体策=必須条件” である。 即ち、組織人としてやらなければならない行動が基本動作12項目であり、基本 基本動作の習得はCSの基本であり、営業力の強化、クレームの予防策として 基本動作には12項目あります。 2.身だしなみ 3.発 声 4.朝 礼 5.電 話 6.指示命令 7.報告・連絡・相談 8.会 議 9.クレーム対策 10.整理・整頓 11.接 遇 12.基本姿勢 基本動作の訓練はいつでも、どこでも誰でもが、お金をかけずに実行できるもの 基本とは「やらねばならないこと」であり、それは挨拶であったり、笑顔であ これら基本がなされなければ、お客さんからの感謝・感心・感動も、お客さまから それはあなた自身の魅力でもあるのです。 挨拶のよくできる人とそうでない人とでは、 やらねばならないこと(=基本)を、当たり前
・やらなければならないこと ・やってはならないことはやらないこと あなたの仕事は、やるべきことをやり、やってはいけないことをしないことが重要 これは当たり前のことですが、非常に難しいことでもあります。 やって当たり前、やれて当たり前のプロの世界にあなたは居るのです。 基本動作とは「基本」を当たり前にやることをいいます。 基本動作は人材育成と平行して行うことで効果が倍化します。 インスタントな方法を求めがちな時代のなかで、この基本動作を徹底することの 商品に大きな差異がない中で、競合と差別化する方法はサービスしかありま どんなにすばらしい商品があっても、最後には人が関わってきます。 自分では一生懸命やったつもりでも、評価するのはお客様です。 お客さんから「感謝・感心」されるだけではたりません。 そこに「感動」がなければならないのです。 お客さんは自分を大切に扱ってくれているかどうかを感じ取るのに敏感です。 どんなにすばらしい商品・サービスを提供したとしても、お客様が本当に満足 あなたの挨拶、身だしなみ、態度はお客様を不快にしていないだろうか。 「お客様は見ています」あなたの一挙手一投足を。 |
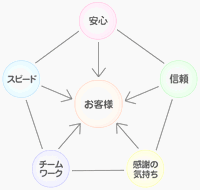
組織人としての基本動作とは
| 5Sは経営改善の基本 |
| M&Aの神様といわれる日本電産永守社長が語る企業再生の極意。 日本電産は世界各国で30社以上の積極的なM&A戦略で業績を拡大してきた。 そのカリスマ経営者、永守社長は世界各国にある人種や考え方の違う企業を再建するための 社員のクビをいっさい切らずに全ての会社を再生を果たしている。 最も重要視されているのが「6S・3Q」である。 そして、「6Sのできていないで儲けている会社があれば1億あげる」と言ってきたが、 5Sは製造業・サービス業などの職場環境の維持改善で用いられるスローガンで6Sは 作法は、正しい行動ができる社員。 そして、これらを確実に実践することで、「会社は儲かるようにできている」は至言で これを実践すると「3Q」、つまり「良い社員(Qualityの高い社員)」、「良い会社 これらのことは決して製造業・サービス業に限った事ではなく、すべての営業会社に ■5S活動とは 5Sは基本動作(12項目)の一部になります。 5Sとは、整理(Seiri)・整頓(Seiton)・清掃(Seisou)・清潔(Seiketu)・躾 5S活動とはこれらを全社員が徹底していくことであり、すべての会社にとって有益な 5S活動の本当の目的はたんなる「職場の美化」ではなく、活動を通じて生産性向上など まず始めに5つのSの意味について確認してみましょう。 なお、最初にあげる3つのSは5Sのなかでも基本中の基本として3S(サンエス)と呼ぶ ・整理…事業活動に必要なものと不要なものをはっきりと区別して不要なものは捨 ・整頓…誰もが必要なときに必要なものを効率的に取り出せるように配置すること ・清掃…汚れやゴミをなくして職場をきれいな状態にすること ・清潔…上記の3Sがつねに維持されているようにすること ・躾……決められたルールをきちんと守らせること しかし、実際に5Sをきちんと行うのは簡単なようで難しいのが実情です。 例えば、「使用したものは必ず元の位置に戻す」「自分の机は常に綺麗にしておく」 5S活動によって、職場の見た目がきれいになるだけでも一定の前進といえますが、 現在、企業規模や業種を問わず、5Sに取り組んでいる企業は数多くみられます。 なぜこのように多くの企業が5Sに取り組んでいるのでしょうか。 それは、5Sに取り組むことで企業にとってプラスとなる多くの効果が期待できるから それは、整理・整頓・清掃・清潔・しつけという5つが工場管理の基本であるからです。 製造業では5Sを実施することにより、無駄な作業がなくなり生産性が向上するとともに、 また、不要な物を処分することで適切な作業スペースが確保でき、労働災害の減少にも 清潔に保たれた職場で仕事をすることで、自分自身の身だしなみにも気を使ったり、 また、お客様が来社された場合に、きちんと片付いている職場と乱雑な職場から受ける こうした従業員の意識は、取引先など社外の人に対して好印象を与えることに加え、 5S活動は「短期的」には社員の負担が増すことになります。 また、「整理・整頓なんてやっても売上が増えるわけではない」など社員からの反発も 社長はこのような反発に対して、活動の本当の目的と重要性をはっきりと示す必要が 5S活動成功のためには全社的な取り組みが不可欠です。 たとえば、A部門で整理や整頓が徹底されていても、B部門の職場は相変わらず乱雑 A部門のメンバーたちもいずれはやる気を失ってしまうでしょう。 推進のためには社長をトップとする全社横断的な体制を組む必要があります。 活動にあたってはいつまでに何をするのかをはっきりとさせます。 たとえば5Sの第一歩である整理については「全部門が1カ月以内に完了する」といった さらに何がどのような状態になったら整理が完了したとするのかなどの判断基準も □「整理」で不要品を捨てる 5S活動の第一歩は整理を徹底することです。 整理とは「事業活動に必要なものと不要なものをはっきりと区別して不要なものは捨てる 当たり前のことのようですが、会社ではそれがなかなか実行できません。 職場にあふれる物を、必要な物と不要な物に分け、不要なものについては処分します。 整理を行うことで、職場から不要な物が減り、仕事がしやすくなります。 例えば、職場にある物を「よく使う物(日常的に使う)」「時々使う物(2週間に1回 その際、不明物には品名や使用部署、当該物の状態、確認期限などを記したカード(目立つ
整理候補の対象品と、その最終的な処置に誰が責任をもつかを決めることも重要です。 整理対象候補となるものは、誰にとっても使用頻度が低いのが通常です。 あらかじめ責任者を決めておかないと、「それは私には判断できない」という理由から、 整理を進めていくと、「今すぐにはどうしても判断できない」というものも出てくるで その場合は前述のような「廃棄予定札」を貼っておき、判断期限を決めておくことが大 「いつか使うかもしれない」と考えて、ずっと保留にしてしまえば整理は進みません。 また、保留品のなかで動かせるものについては、保留品保管棚を作っておき、期限 保留期限を過ぎても棚に残っているものは処分します。 ・必要、不要の基準と処分の方法やルールを決めます。 ・必要かどうか分からない物は、一カ所に集めて関係者に確認させます。 ・確認するものには、「赤札」を付けておきます。 ・確認の期間を決めておきます。 整理が進まない最大の理由は、多くの場合、「捨てるべきものと、とっておくべ プライベートな場面では「不要品はすぐに捨てる」という人でも、会社ではそれ 自分の判断で捨ててしまって、後に「あれはやっぱり必要だった」ということに したがって、あらかじめ会社としての「不要品基準」を定め、それをルールとし 万一、後日捨てたものが必要になったとしても、捨てた人はあくまで基準 会社の職種や業務サイクルによっても変わりますが、たとえば、 ・過去3カ月間1度も使わなかったものは捨てる ・今後3カ月間使う予定のないものは捨てる ・修理不能な機械や新型モデル導入後の旧型機械は捨てる といった明確な基準を定めることが必要です。 自分ひとりではどうしても判断できないものについては、「廃棄予定札」を貼っ
「整頓」とは、物の配置を決め、必要な時に必要な物をすぐ取り出せるようにしておく 整頓を行うことで、「必要な物がどこにあるのか分からない」という状態をなくし、物を 具体的な整頓の進め方は、「どこ」に「何を」置くかを決め、それを誰が見ても分かる また、「どれだけ」あるべきかを決めることも大切です。 しかし、必要以上の在庫を抱えることはスペースを無駄にすることであり、資金を固定化 さらに、適正な在庫量の基準がないと、発注担当者によって追加注文のタイミングや 「どこに何を置くか」を掲示している例としては、スーパーマーケットの売場を思い浮か スーパーマーケットの売場では、エリアごとに吊り看板などで品目を表示するとともに、 プライスカードの目的は本来「客に対して商品の価格を示す」ことですが、プライ 定位置を決めるとは、そのものが本来置かれているべき場所を決めることで 経験の長い人はどこに何が置かれているかは理解しているはずですが、それ 経験者が休んだ場合などには、「いったいあの部品はどこにあるのか」といっ 誰でもすぐに必要なものを見つけられるようにするためには、各部品の定位置 その際には次のような点に留意しましょう。 ・使用頻度の高いものほど作業者の近くに配置する ・使用頻度の高い部品は「先入れ先出し」の配置とする(蓑から投入し ・全体の作業工程を考えた効率的な配置にする(原則として作業順序に ・棚の高さなどは作業者が楽に取り出せるよう工夫する ・キャビネットや道具箱など内部が見えない空間はできるだけつくらない。 ・机の中などの個人管理はやめて、誰の目にも触れるオープン管理にする 整頓では「どこ」に「何が」あるかだけではなく、「どれだけ」あるべきかを決める 工場で大量に使用する部品やオフィスでの消耗品などは在庫が底をつくこと しかし、必要以上の在庫を抱えることはスペースを無駄にすることであり、資 また、適正な在庫量の基準がないと、発注担当者によって追加注文のタイミン 過去の使用量の推移、発注から納品までのタイムラグなども考慮して、「在庫 使ったものはすぐに元の場所に戻さなければなりません。 しかし、ものを探すときは必要に迫られて必死に探しても、使い終わった後にそれを せっかく整頓のためのさまざまなルールを決めても、それが維持できない大きな原因 きちんと戻させるためには、各人の整頓への意識を高めるとともに、終業時のチェック また、「工具類は置き場所に工具の形をした線を引く」など、戻す際の負担を少しでも 整頓を徹底するためには、「楽に探させる」以上に「楽に戻させる」ことが重要とも 整頓のポイント ・基本的に目で見て分かる整頓を行います。 ・使用場所や使用頻度、移動の容易性などで保管場所を決めます。 ・保管場所の定位置を決め、分かりやすく表示します。 ・保管場所や保管量をルール化して明文化します。 「清掃」とは、職場のゴミをなくし、汚れのない状態にすることです。 特に製造業の場合、工場内のゴミや汚れは異物混入などにつながり、製品の品質を左右す 清掃を徹底することでそうした事態を防ぎ、製品の品質を保つことができます。 具体的な清掃の進め方は、「1つ作業が終わ る度に作業場所の周辺を清掃する」「毎週月 そしてルールに従って全員で清掃に取り組みます。 こまめに清掃を行うことで1回当たりの清掃時間を短縮することができ、忙しくても清掃 なお、こまめに清掃を行うためには、清掃用具を使いやすいように整えておくことも重要 清掃用具は、取りやすいように職場内で何カ所かに分散させて置いておくとよいで 清掃とは「汚れやゴミをなくして職場をきれいな状態にすること」です。 気付いた人が気付いたときに清掃するというやり方ではなく、きちんとルール化して会社 また、清掃時のチェックポイントを工夫することで日常的な点検につなげることもでき チェック表を用意するなどして誰もが同じ視点で清掃点検ができるようにしましょう。 ほとんどの人は自分のデスクや作業場の周辺に目につくゴミが落ちていれば しかし、通路などの共用部分については、積極的にゴミを探して片付けようと また、目につきにくい部分にたまった挨などは長期間放置されることもある。 清掃においては自分の周辺だけではなく、共用部分(OA機器の周辺、会議 共用部分の担当者は月ごとにローテーションさせるのもよいでしょう。 また、清掃の方法(掃く、拭くなど)や頻度(毎日、週1回など)についてもルー そして、清掃は重要な業務の一部として明確に位置づけます。 ルールどおりにきちんと運用していけば、自分の担当以外の場所でもゴミが落 自分の手で清掃するということは、対象物を入念にチェックすることでもありま たとえば、普段は機械で洗車を済ませている人が、たまに自分自身の手で入 また、思ったよりもタイヤの摩耗が進んでいるといった安全面に直結すること 職場における清掃においてもたんに汚れを落とすだけではなく、清掃中に「機 もちろん清掃だけですべての点検を済ませることはできませんが、毎日の清 チェック表を用意するなどして誰もが同じ視点で清掃点検ができるようにしま ・まずは職場をきれいに掃除します(床、壁、窓、設備、机など)。 ・清掃のタイミングなどをルール化して、全員で清掃に取り組みます。 ・製造機械などの設備は、設備ごとに清掃マニュアルを作成します。 ・清掃用具は使いやすい状態にしておきます。 5Sでいう「清潔」とは3S(整理、整頓、清掃)がつねに維持されているようにすること 3Sはそれぞれにルールを決めてそれを実行することでいったんは実現します。 しかし、その状態を維持していくことは簡単ではありません。 たとえば、活動導入当初は積極的だった人も忙しさを理由に手を抜き始めること また、日々会社の状況は変わっていきますから、3Sのルールをマイナーチェン このような事態に的確・迅速に対応していくことが「清潔」ということになります。 さらに清潔には3Sレベルを向上させていくという意味合いもあります。 たとえば、「整理」で不要品が一掃されるのはよいことですが、その前段階として 同様に工具や部品の種類を減らすことができれば整頓に必要な手間は減りま このように清潔とは3Sを一時的な状態に終わらせずに、長期にわたって維持・ 整理・整頓・清掃の仕組みを維持し、職場を常にきれいな状態に保っておくこと 具体的な進め方は、チェック表を作成し、整理・整頓・清掃の状況を定期的に確認する 確認→改善→確認→改善という流れを繰り返すことで、清潔が保たれるようになるのです。 なお、確認は、経営者や工場長など、職責が上の人間が行うようにします。 これにより確認時の甘えや馴れ合いをなくし、清潔の維持を徹底することができます。 また、チェック表を作成する際には、 ・チェック項目は実際に現場を見てできるだけ具体的に記述する ・項目ごとの評価は5段階や10段階などで評価し、前回の確認時から などに注意すると、効果的なチェック表が作成できるでしょう。 ・定期的に職場を巡回し、清潔の維持状況を確認する。 ・確認は上席者が行うようにする。 ・定期確認用のチェック表を使用し、明文化された基準に従って確認を行う。 ・チェック表にない指摘点があった場合には、現状を写真に撮っておき、 「しつけ」とは、ルールを順守を習慣化させることです。 従業員に対し、当たり前のことが当たり前にできるように指導・教育していくことが 具体的な進め方は、就業規則や職場のルールを従業員に対してしっかりと通知します。 そして、「就業規則に定められたことは守ること」「職場で働きやすくするために、皆で また、「今さら言わなくても分かっているだろう」と考え、そうした教育を怠ってしま 私たちは子ども時代から親や年長者による躾を受けてきました。 やってよいことといけないことについて徹底した指導を受けたおかげで、日常生活では さらに会社で守るべきルールのなかにはすべての社会人が守るべきルールだけではなく、 たとえば、食品工場で働く人には通常のオフィス勤務の人とは比べものにならないレベル また、建設現場など危険を伴う職場では安全基準が細かく決められているでしょう。 自社の社員に対して、自社のルールを詳細に説明して、それを確実に守らせていくことが ルールブックを渡して「このとおりにやれ」と指示するだけではなく、ルールを決め また、躾は月に1度まとめて行うというものではなく、毎日少しずつ積み重ねていく 社長は常日頃から経営幹部などへの躾を行うとともに、彼らが部下に対して適切な躾を さらに社長自身についても、自分が部下を躾けるにふさわしい行動ができているか ・職場のルールは全員に確実に通知します。 ・ルールを守ることの重要性を繰り返し説明します。 1.職場安全の確保や向上につながる。 2.職場がきれいになり、仕事がしやすくなる。 3.仕事が楽しくできるようになる。 4.無駄な在庫がなくなり、在庫の量や場所がすぐ分かるようになる。 5.時間の無駄がなくなり、コストダウンにつながる。 6.結果的に生産性が向上して利益率が上がる。 7.全員で取り組むことにより、職場に一体感が生まれる。 1.従業員の意識付けが重要 5Sの導入に当たっては、専門的な知識などは必要ありません。 心がけ1つで誰でもすぐにでも実施できます。 その一方で、誰でもできることだからこそ、5Sに対する従業員の意識がその効果に そこで、ここでは従業員の意識を高め、活発な取り組みを維持するという観点から、 5Sの導入に当たって、経営者(工場や支店などの組織単位で5Sに取り組む なぜ5Sが必要なのか、5Sを導入することで「どういった効果が期待できるのか」 という意識で5Sに取り組むことになります。 それでは5Sは表面的な活動にしかならず、大きな効果は見込めないでしょう。 そうではなく、5Sを実践することによって自分の仕事がやりやすくなるなど、 「上司からの命令で仕方なく」行うのでは、「一見きれいに整頓されている すると、何か必要な物があるときにはやはりその物を探す時間が必要となり、 整頓にかけた時間が無駄になっただけです。 一方、「自分のために」整頓を行うと、従業員は「最も効率がよくなる置き方」 探す時間が不要となって作業効率の向上につながることになるのです。 作業効率の向上という効果を従業員が実感できれば、整頓に対するやる気は 従業員に対して5Sの意義をしっかりと説明し、「自分のため」という自主的な取り組み これまで5Sに取り組んでいなかった企業が新たに5Sに取り組む場合、5Sの取り組みは 負担を求める以上、部署や役職などにかかわらず、全員平等に負担してもらわなければ 5Sは業務改善に有効であるので、企業にとっては「本業」といえます。 しかし、5Sは一見すると企業の本業ではないように感じます。 このように、本業ではないと思ってしまうと、そこに時間を使うことを嫌がる従業員も しかし、だからといって「手が空いている人」だけで5Sを進めることはよくありません。 こうした進め方をしてしまうと、取り組みに参加しない人が出てきます。 特定の人だけが5Sに取り組んでいる状況では、「忙しい中時間を工面して5Sに取り組ん これでは不公平だ」という、従業員の不満につながります。 場合によっては、取り組みに参加していない従業員からも「自分はこんなに忙しいのに、 業務量に差がありすぎるのではないか」などと不満が出てくるかもしれません。 もちろん、職場に暇を持て余している人などいないはずなので、これは正当な主張とは しかし、一部の人だけで取り組みを行うと、こうした不満が出てくる可能性もあるのです。 業務を効率化し、仕事の質を向上させるための5S導入のはずが、かえって職場の不和を 5Sの実施に当たっては、全員で取り組むことが重要です。 全員で取り組むことが重要というのは、社長や役職者といった経営幹部であっても例外 役職者の中には「5Sは部下がやることであって、自分の仕事ではない」と考える人もいる 社長が自ら率先して5Sに取り組むことで、 「社長が取り組んでいるのだから、自分もやらなければ」と、こうした役職者にとって そして、役職者が取り組むようになると、それを見た部下達も取り組むようになります。 逆に、社長が指示だけ出して自分では5Sに取り組まないようでは、従業員はついてこな こうして考えると、社長自らが率先して取り組むことで、5Sが全社的な取り組みとして ここまでは従業員の意識付けという観点から5S導入の留意点をみてきました。 5Sを導入し、徹底していくためには、それを実践する従業員が高い意識を持って取り組む しかし、従業員に対して5Sの重要性を説き、5Sを徹底するようにと号令を掛けていれば 5Sを徹底するためには、社内で5Sのルールを定めておかなければなりません。 ただ単に「きれいにしなさい」と言われても、従業員はどの程度までやればよいのかが こうした状態では、従業員は自分が求められている取り組みのレベル、特に、「最低限 そのため、最初はしっかりと5Sに取り組んでいても、周囲の取り組みのレベルや確認者 そこで、5Sの導入に当たっては、まずは従業員が守るべきルールを設定します。 その際、ルールは必ず明文化するようにします。 そして明文化したルールは、全従業員に通知し、徹底させます。 ルールを通知するためには、職場に貼り出したり、朝礼時に唱和したりするのもよいで ルールの設定は、5Sの導入に当たってまず頭を悩ませるところです。しかし、5Sの まずは標準的なルールを設定し、運用しながら自社に合った形に変えていけばよいでしょう。 標準的なルールとしては、例えば、机上の整理に関しては ・勤務中は作業上必要なものは机上に置いてよい。作業が終われば速やかに片付ける ・休憩などで離席する場合は、資料や文房具など机上の物をきちんと整える ・終業後や外出時は、机上に物を置かない。ただし、電話、パソコンなど移動が困難な これを、運用していく中で自社に合わせた形で追加・修正を加えていけば、自社に合った なお、最初に設定するルールは、少し厳しく感じるくらいでよいでしょう。 例えば、「机上には物を置かない」というルールがあると、従業員は机上の物を何とか しかし、これを「机上には必要な物以外は置かない」とすると、「必要な物だから置い ◎まずはできることから 先述の通り、5Sは仕事をする上では「当たり前」のことです。 例えば整理・整頓をとってみると、整理・整頓が重要なことは誰でも分かっています。 それにもかかわらずできていないということは、日常の業務が忙しく整理・整頓を そのことを考慮せずに、「今日から5Sを徹底します」といっても、やはり無理があり 何事も、高すぎる目標は到達意欲をそいでしまうため、目標は段階的に設定するのが これはもちろん5Sにおいても同様です。 5Sを導入する際には、最初から完全を目指すのではなく、まずはできることから始めて、 その場合、一般に、整理・整頓・清掃という「3S」から始めて、それらができたら まずは月に一度でも日を決めて全員で3Sに取り組み、それを繰り返しながら3Sが常態化 5Sの取り組みを維持していくためには、5Sの取り組みにおける各人の責任を明確にする 各人の責任があいまいな状況では、従業員に「誰かがやるだろう」という意識が生じ、 また、「多くの人は自分の机を片付けるだけで、共用部分の清掃はいつも決まった人が そこで、 各従業員に5Sの担当エリアを設定する ことで、各人の責任を明確にするとともに取り組みの差をなくして、5Sの取り組みを 担当エリアを決めたら、職場をエリア分けして担当者の名前を書き込んだ「5Sマップ」 なお、この場合もやはり社長や経営幹部にも担当エリアを設定し、全社的な取り組み 社長にも担当エリアを設定して取り組みを行うのであれば、社長は5Sの社内ルールを 従業員への刺激とするためにも、社長は社内ルールで定めたよりも厳しい基準で5Sに
|





組織人としての基本動作とは
| 店舗経営に欠かせないクリンリネス |
|
一般的にクリンリネスは店舗運営(外食産業、カフェ業界、宿泊業、整備業界)において 事務所などでは基本動作(12項目)がこれにあたります。 ほとんどの若いユーザーや女性客はきれいな店舗や工場を好んで求め、きたない これは若いユーザーや女性客に限らず、すべてのユーザーに言えることです。 今では、クリンリネスが店舗や工場を選ぶ時の基準になっています。 例えば、一日中、いろいろな型式や大きさの車が出入りし、様々な故障を分解し、 いくら朝晩全員で一生懸命に工場内を清掃しても、 入庫がたくさんあって忙しく、盛業中のお店や 1.大切なお客様が来店されても「来客専用駐車場」が設定してなかったり、あっても 2.フロントのカウンターの上に、雑然と商品や 3.工場内は全体に暗くて、壁には部品や工具が雑然と掛けてあり、リフト回りには取 4.駐車スペースには、完成車、待機車両、代車やサービスカー、個人車両が前向き、 5.工場の周囲には、ドラム缶やペール缶、古タイヤにバッテリー、取り外した板金物 1.パブリックスペース(お客様スペース) お客様専用スペースであり、最高度のクリンリネスを確保し、プライベートスペース ・事務室、受付カウンター、商談コーナー、待合スペース、カタログラックや 社員が更衣したり、食事や休憩したりするスペースは当然必要です。 さらに書類や物品の格納庫や会議室などもプライベートスペースになります。 ・休憩室(昼の食事と休憩、午後の休憩時間にはここでゆっくりと寛ぎ、疲れ クリンリネス(清潔さや清潔感の維持向上)には整理整頓と清掃の実行が不可欠です。 1.整理整頓(不要な物を捨てる) 社内では毎日毎日多くの不要物が発生します。 ゴミのように誰が見ても「捨てられる」ものばかりではありません。 廃棄を即断する最も難しい代表は「大物部品のコア」や「補修し再利用可能な板金物」 あれも必要、これも必要と保管しておくと場所も取られますし、 第一ステップで不要な物を捨てたら、第二ステップは、 従来はとかく社員にとって便利なところに優先配 合理的な置き場所を考え決めても、使った社員全員が使用後に必ず元に戻す 最終的にクリンリネス維持向上にとって「社員のしつけ」が最も重要に どこの工場、店舗でも「朝晩の清掃」は当たり前として実行されています。 ここではその方法見直しについて考えてみたいと思います。 多くの工場・店舗の朝晩の清掃方法を見ますと、床の汚れをなくすことが主眼の クリンリネス維持向上を目的とした朝晩の清掃は (1)整理整頓3つのステップを基準にして不要な物が新たに発生してないか、決 (2)床はもちろん、壁や天井も含め徹底してきれいにすることを意味します。 作業を完了したらその都度ストール周辺を清掃することも大切です。 作業に使った工具や部品、消耗品などを元に戻し、次の作業を行うために清掃 床やリフトに油は付着していないか、小さい部品が足元に散乱していないか、作 事務室内でお客様が帰った都度、応接セット回りを清掃するのも同じです。 灰皿を洗い、出した湯飲みを片付け、使った読み物などを所定の位置に戻し、 汚すから清掃が必要になるのです。 汚さなければ清掃したままの状態が維持できます。 店舗や事務所のようにお客様が来店されて、そのお客様が汚すような場合に清 全く汚さずに仕事はできないかも知れませんが、クリンリネス維持には、「汚さな |


組織人としての基本動作とは
| 接遇マニュアルの作成 |
|
1.“接遇”と商品・サービスは一体 礼儀正しく、気持ちのよい接遇はお客様に好印象を与え、企業のイメージ向上に どんな企業にも接遇マナーは必要ですが、特に小売店や飲食店などお客様と接 △△店と○○店では立地や店舗面積などに大きな違いはなく、商品の品質や価格 このように、店舗の大きさや商品に特別な また、わずかながら△△店の商品の品質 そのため企業は、いま一度、自社の接遇 接遇は他の基本動作11項目の総合的な意味合いを持ちます。 接遇マナーというと、細かく規定されたルールを想像するかもしれません。実際、 企業全体として接遇マナーを標準化するうえで、接遇マニュアルを作成することは ただし、忘れてならないのは接遇マニュアルを実行するのは従業員であるという ・接遇マニュアルが従業員に周知徹底されていない ・“接遇”の意識に欠ける企業風土である などの場合、マニュアルはほとんど機能しません。 誰に教えられたわけでもないのに“接遇”の意識が高い従業員がいる一方で、全く そのため、“接遇”の意識を数学のように定型化された教育方法で教えるのは難 従業員は自分の上司を模倣することからビジネスを覚えていくものです。 上司の接遇マナーがしっかりとしていれば、従業員は 1.接遇マニュアルの重要性 企業全体としての“接遇”の意識を高める 接遇マニュアルを作成することによって、 また、企業全体としての接遇マナーも 例えば、同じ企業であっても「CさんとDさんでは接客態度が大きく違う」といったケ “接遇”の意識は全従業員に周知徹底されたものでなければなりません。また、どの そのために、接遇マニュアルは不可欠なものといえるのです。 接遇マニュアルに記載すべき内容は幅広く、また企業規模や業種などによって異 (1)接遇マニュアル作成チームの発足(あるいは、担当者の決定) 接遇マニュアル作成チームを設立し、そのチームが中心となってマニュアル作 その際に検討することは、 ・チームをどの部課に設置するか ・どのような従業員をメンバーとするか 企業にはさまざまなマニュアルが存在します。 例えば、物流業者であれば「車両運行マニュアル」「事故対策マニュアル」など これらのマニュアルを利用することが多いのは基本的にドライバーです。 また、マニュアルにはドライバーの経験に基づく考えを盛り込まなれば実効性 このように、利用者が特定の部課あるいは従業員に偏りがちなマニュアルにつ 一方、接遇マニュアルには「来客応対」など全従業員共通の事項が多く含まれ そのため、接遇マニュアルの利用者が特定の部課あるいは従業員に偏ること このような理由から、接遇マニュアル作成チームは総務部内に設置するのが なお、総務部など部課が明確に分かれてない場合は、接遇マニュアル作成担 担当者選抜の考え方は、前述した接遇マニュアル作成チームの時と同様です。 つまり、「社内全体を見渡すことができ、 接遇マニュアル作成チームが行う最初 一口に接遇マナーといっても、その範 例えば、基本的なものだけでも、 ・来客時の接遇マナー ・電話応対時の接遇マナー ・他社訪問時の接遇マナー ・席次に関するマナー といったようにさまざまです。 さらに、業種によっては「店舗接客マナー」などが不可欠なケースもあります。 このように、接遇マナーの範囲は非常に広いため、一つ一つ確認してい ては長 そこで、接遇マニュアル作成チームは ・接遇マニュアルに盛り込むべき項目の案を決定する ・項目を「共通マニュアル」と「個別マニュアル」に区別する といったことを行いましょう。 「共通マニュアル」と「個別マニュアル」とは、 ・共通マニュアル:来客時のマナーなど、すべての従業員が利用するもの ・個別マニュアル:店舗接客マナーなど、利用が特定の従業員(販売員) といった区分です。 2つのマニュアルのうち、接遇マニュアル作成チームが一から作成していくの 一方、個別マニュアルには担当者(現場)の意見を反映させる必要があるため、 「共通マニュアル」と「個別マニュアル」を区分することで、接遇マニュアルは この区分により、接遇マニュアル作成チームは、はじめに「共通マニュアル」の ここまでの流れは、接遇マニュアル作成手順の一例であり、実際に作成する際 また、どのような方法で接遇マニュアルを作成した場合でも、接遇マニュアルの 接遇マニュアル作成チームが確認して、内容や誤字脱字をチェックした後に、 この段階で部門長から修正を指示されることもあるはずです。 指示された部分を一つずつ確実に修正した段階で、接遇マニュアルは完成し 完成した接遇マニュアルは、社内の分かりやすい場所に備え付けます。 また、従業員に接遇マニュアルの確認と実践を呼びかけましょう。 全従業員に周知徹底されていない接遇マニュアルでは実効性がありません。 接遇マニュアルは、企業全体の“接遇”の意識を高めるものであるため、利用されなけれ また、従業員の接遇マニュアル利用を促すためには、企業経営者や経営幹部が率先して 接遇マニュアルは、「品質管理マニュアル」などよりも不変性が高く、見直しがされる しかし、全く見直しを行わないのは問題です。 そこで、接遇マニュアル作成チームが中心となり、定期的に接遇マナーの徹底状況を 接遇マナーがしっかりと実践されているうちは、接遇マニュアルが機能としていると考 一方、接遇マニュアルが作成されたにもかかわらず、接遇マナーがあまり徹底されて 仮に、接遇マニュアルの実効性が乏しいと感じたら、従業員の意見なども取り入れな そうではなく、そもそも従業員の“接遇”の意識が低いようであれば、企業経営者や経営 接遇マニュアル作成チームは、マニュアル作成のためだけに組まれたチームでは 1.礼儀正しい態度 ・お客様だけでなく、上司、同僚、部下にも礼儀正しい態度で接します。 ・どんな時にも相手の立場を考えて、発言・ ・どんな方でも、お客様であることに変わり ・上司、同僚、部下は共に働く仲間です。 ・人と人の出会いは第一印象が大切です。 清潔度チェックリスト
|




組織人としての基本動作とは
| 整理・整頓 |
| ■整理・整頓 整理・整頓という言葉を聞くと子供の頃を思い出します。 しかし、社会人になっても整理・整頓の下手な人が多いようだ。 従業員の机の引き出しの中に私物が入ったりしていないだろうか? 整理・整頓は会社(店)レベルの鏡であり、仕事の能率を左右します。 整理・整頓の基本は「決める」、「戻す」、「捨てる」です。 整理整頓こそ、仕事に取り込む社員の姿勢が具体的な形として表われ、良き職場 社内における多くの問題(ムリ、ムダ、ムラ、クレーム、ミス)発生は整理整頓で決まり 1)仕事は整理整頓に始まり整理整頓に終わる、整理整頓なくして企業の合理 2)整理整頓はしつけと規律ある社風の窓であり鏡である。 3)整理整頓の基本は「決める」「捨てる」「戻す」
1)目的の明示…何を整理整頓するのか、目的を明確にする。 ○必要に応じて責任名を明示する。 イ)共通したもの、類似したものをグループ化する。 ウ)グループ化したものにウエートづけをする。 エ)それに従って大、中、小の項目に分ける。 オ)いらないものは捨てる。
1)掃除用具その他共通道具は、その置き場を一定にして、責任者及び、位置 2)整理保管箇所を明示し、保管要領を示す。どこにあるか、誰でも分かるように 3)廃棄物処理場の場所を定めておき、処理基準を決める。
1)常時使用するもの、時々使用するものを区分し使用ルールを決める。 2)使用方法、ルール、特性などを周知させる。 3)共用物は誰が使用中か分かるようにする。(貸出ノート作成など) 1)破損、不足の場合の処置のとり方を定める。 2)使用後返却する場合のルールを決める。 3)収納要領を具体的に話す。
1)書類資料などは、保管、保存期間及び場所を決める。 2)保管期間を経過した書類、資料などは定期的に一箇所に集める。 3)保存の為、不要書類の「抜き取り」や「置き換え」をする。 4)保存品は品名、期間、責任者などをカラーで明示する。 5)主題別、相手先別などに区分し収納する。
1)廃棄する場合は担当責任者に連絡して適否を問い合わせる。 2)廃棄するものは(仕分け、焼却、廃棄、売却)する。
|
お問合せ・ご相談はこちら
企業運営に欠かせないマーケティング、業務改善、リスクマネジメントの3つの仕組みづくりを
倒産に見舞われています。「知っていれば」「対策を講じていれば」倒産を防げたはずの企業が多く存在する
ことを、私たちは数多く見聞きしています。
事業運営に欠かせないマーケティング、業務改善、リスクマネジメントの分野で全力を尽くして支援して
まいります。
| 対応エリア | 静岡・愛知県内、東京周辺 |
|---|
新着情報
- 詳細はこちらへ
