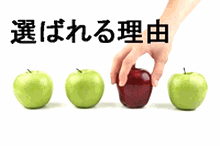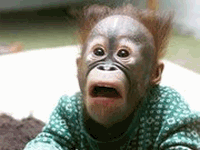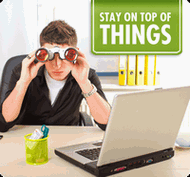〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町2-26-501
ユニークセリングポイント(USP)
10、20年前のやり方や考えを今も続けていないだろうか。
■作れば売れた時代から作っても売れない時代
今では、作れば売れた時代から作っても売れない時代にあります。
モノをモノとして売っていては売れない時代なのです。
単なるモノとしてではなく、顧客の抱える悩みや問題の解決手段(コト)としてあなたの商品・
サービスがあるということを理解する必要があります。
今ではIT環境の進化により近代の武器があります。
しかし、残念ながら十分に活用されていないのが実態です。
あなたもご存知の「富山の薬売り」(江戸時代)からデータベース・マーケティングは存在して
いました。
顧客の家庭状況をつぶさに書き留めた懸場帳(かけばちょう)は有名で、このデータは他業界にも
高値で売れていたそうです。
しかし、今でも営業の多くが攻略先を調べずに場当たり的に訪問していることです。
「敵を知り己を知れば百戦殆からず」の言葉にあるように、攻略するマーケット(市場)の
内情を知らずに営業活動をすることは竹槍で戦うようなものです。
1.自社を知る
自社を知るうえで、一番簡単な方法を紹介します。
それは、「USP」を知るということです。
USPとは、「Unique Sales Proposition」の頭文字をとった略語で、会社の独自性のことを表す。
あなたの会社は何かしらの強み、利点、特徴があるから顧客に選ばれるのです。
その長所、利点を自ら確認することで、自分の会社は何が得意で、何が不得意かが分かってくる。
USPを知るための方法として最も簡単なのはヒアリング調査です。
どの会社にも営業部や支店、店舗などの顧客と接する最前線の部署があるはずです。
この部署を活かして、自社の商品やサービスを購入した顧客に質問し、回答を得ることです。
あなたの業界でも収益を上げ続けている会社があるはずです。
その会社が「なぜ 利益を出しているのか?」という疑問を持つことです。
そして調べることです。
しかし、同業者ではなかなか教えてくれないでしょう。
ですが、他業種であれば門戸を開いてくれる可能性は大です。
他業からであっても真似る(学ぶ)ことは多数あります。
2.「決めたことを決められたとおり継続実行する」
簡単なようでできていないのが多くの中小企業の実態です。
それは結果として業績ダウンといった形で表面化します。
業種業態を問わず事業を運営しているすべてが営業会社といっていいでしょう。
営業会社であれば、継続して利益を出していかなければなりません。
しかし、中小企業の大多数が喘いでいます。
決めたことを継続実行することができれば必ず売上はアップするはずです。
できないのには理由があります。
業務の多くが我流であったり、場当たり的に行われていることです。
結果的に組織全体が熱意といった精神論を主体とした体制になってしまっている。
言い換えるなら、仕組みのない烏合の衆の集合体になってしまっているからです。
やることが場当たりであることで、人件費は存在給と化してしまっている。
「愚者は自分の経験から学び、賢者は他人の経験から学ぶ」の言葉にあるように、成功している
会社を真似ることです。
「真似る」は「学ぶ」に通じる。
3.「行動するリスク」と「行動しないリスク」
足元の利益ばかりに目を向けていては会社の存続は危ぶまれます。
「経営において、100万円の利益を出すことと、100万円の損失を未然に防ぐことは同じ価値を持つ」
危機管理のできている会社はほんのわずかです。
これも場当たりな経営が要因のひとつとなっています。
各種対策のためのマニュアルは作ったが作成が目的となり、マニュアル自体は形骸化されてしまっ
ていることを多数見聞きしてきました。
「仕組みづくり」は会社の使命である継続的に収益を上げる存在であるために欠かせません。
今あなたは「何もしないリスク」と「行動するリスク」どちらを選択しますか?
協業のご案内
メルマガ登録(無料)はこちら
お問合せ・ご質問はこちら
ユニークセリングポイント(USP)
■はじめに
いまの日本企業の多くは、安定を求めすぎて活力を失っていないだろうか。
衰退と繁栄の継続との、両者を分けるのは環境変化の程度の大小といった外部要因もあろうが、
自らが変化を現実として受け止め、逃げずに立ち向かうか否かという内部要因によるところも大きい。
ここでは、繁栄の源泉である「利益」について、どこから創出されるのかについて検討してみます。
□企業の将来性を計る指標
企業にとって「利益」とは何でしょうか。
利益とは、企業に投資された資本の増加額のことであり、企業活動を通じて獲得されるものです。
資本主義の経済社会では、利益を上げられない企業は存続することはできないし、利益を創出する
力が強い企業が、優れた企業とされる。
利益、そして、企業の利益を創出する力を表すための「指標」には、さまざまなものがあります。
まず、「当期純利益」は、企集の活動から得られた経済的な成果のうちの珠主の取り分であり、
株主資本を増加させる要因になります。
その「当期純利益」を「株主資本」で割ったものが、「自己資本利益率」(ROE)であり、株主
から見た投資利益率を表しています。
次に、「営業利益」は、売上高から、それに対応する売上原価と販売費および一般管理費を差し
引いて求められる、言わば企業の本業から得られた利益です。
この営業利益を売上高で割ったものが、「(売上高)営業利益率」です。
この営業利益率は、売上高のうちどのくらいが利益に結びついているかを、示しています。
まずは、日本企業の営業利益率とROEの推移を見てみます。
1960年代から2000年にかけて、営業利益率やROEは、ほぼ一斉して低下してきた。
その反省として、利益率重視の経営が必要とされ、近年、多くの日本企業は、利益率の改善に取り
組んできました。
その結果、2000年前後を境に、日本企業の利益率は上昇額向に転じました。
しかし今では、日本企業の営業利益率や、株主へのリターンを示すROEは低迷し続けています。
日本の株式市場は、世界の中でも際立って低迷していたのです。
日本の上場企業では現在、ROEが長期で8%を上回る企業が半分にも満たない状況です。
その理由は圧倒的な事業マージンの低さ、つまり「事業で儲けていない」ことです。
投資家から見た企業価値は、現在の収益性だけではなく、将来の収益性と成長性への期待によって
決まります。
それを考え合わせると、日本の株式市場の低迷は、投資家の日本企業の将来性に対する悲載的見方
を表していると考えられます。
□「付加価値」が物語る企業の姿
その原因について手がかりを得るために、日本企業の「付加価値」の創出状況を検討してみます。
ここでいう「付加価値」とは、企業による経済活動から生み出される価値のことであり、売上高
から外部に支払った費用を差し引いて求められるものです。
その付加価値から、さらに人件費と賃借料・公租公課を差し引くと営業利益になります。
言い換えれば、付加価値を源泉として、人件費として社員に、営業利益として投資家に、企業が
獲得した価値が分配されるのです(ここでは議論の的を絞るために、支払利息や税額については
省略している)。
例えば、A社が、1年間で、外部から材料を1000万円で仕入れ、それを加工して製品にして、
3000万円で販売したとします。
材料以外の費用として、社員の人件費が800万円、工作桟検を稼動させるための電力科が100万円、
土地の貸借料が200万円、借入金の支払利息が300万円かかったとします。
そして、600万円(=3000万円-1000万円-800万円-100万円-200万円-300万円)の利益が
上がった。
するとA社が創出した付加価値は、1900万円(=3000万円-1000万円-100万円)となる。
付加価値額の算定においては、人件費、賃借料、支払利息は、外部に支払った費用とはみなさない。
材料費および電力科は、他企業の活動成果が、A社での生産のために投入されたことへの対価です。
これに対して、人件費は「労働」、賃借料は「土地」、支払利息は「資本(借入資本)」という、
A社の活動に使われた資源に対して獲得した付加価値を分配したと考える。
また、利益は「資本(株主資本)」への分配額ということになる。
すると分配された金額を足し合わせることで付加価値を求めることもできる。
この場合は、利益に、人件費、賃借料および支払利息を加算して算出するので、
1900万円(=600万円+800万円+200万円+300万円)となります。
経済学的に説明すると、付加価値とは生産高から中間投入額を差し引いて算出されるものです。
生産高は、売上高ベースで考え、モノだけでなくサービスの生産も含む。
中間投入額とは、ある企業の生産する製品・サービスが他企業の生産のために使われた額です。
また分配面から見た付加価値は、各生産要素への分配額を足し合わせて算出される。
生産要素とは生産に用いられる資源であり、主要な生産要素として、労働、土地、資本が挙げられ
ています。
企業は生産要素を活用して付加価値を創出することで、社会の富の増大に貢献しているのであり、
その貢献が経済社会での企業の存在意義です。
つまり、付加価値は、社員や投資家への分配の元になるパイの大きさを示すものです。
その意味で付加価値は、まさしく利益の源泉であり、豊かさの源泉なのです。
日本企業の売上高付加価値率の推移(出典:財務省)を見ると、その動きは営業利益率と大きく
異なっていたことがわかります。
1980年代から2000年前後まで上昇傾向にあった売上高付加価値率は、最近の数年は低下している。
これらの意味するところは何なのでしょうか。
つまり、近年の日本企業の利益率向上は、日本企業が高い価値を創出するようになったためではなく、
人件費として社員に分配する比率(労働分配率と呼ばれる)を減少させることによって、達成して
きたものだといえます。
これをもって、はたして企業の業績が改善してきたといえるのだろうか。
ただしここでは、労働分配率を高めよ、と主張するわけではありません。
近年、日本企業の一人当たり人件費は低下してきた。
一方で、日本企業の利益率はいまだに低く、さらなる向上が求められている。
これ以上、人件費を下げれば日本の豊かさは損なわれ、景気にも悪影響を与える。
だが、利益率を下げるわけにもいかない。
さらに近年の天然資源の価格高藤によって、日本企業の付加価値率は圧迫されている。
日本企業がこのような厳しい状況にあることで、投資家は、その将来の成長性と収益性について
悲観的にならざるをえないのです。
しかし、我々までが、投資家的視点に立って悲観していても仕方がない。
また、創出する価値が増えないことを前提とした、ゼロサムゲームの中で、社員が取るか投資家が
取るか、と分配をめぐって対立しても仕方がない。
大切なのは、日本企業が、豊かさの源泉である付加価値をいかにして創出するか、に焦点を当て、
そのための施策を実行していくことです。
ひとつの国で創出される付加価値の総額は、国内総生産(GDP)と呼ばれ、その国の経済規模や
豊かさを表す指標として用いられている。
個別の企業にとっても、「付加価値」は、利益と同様に、重視されるべき指標にほかならないのです。
□「人件費」はコストではなくリターン
国内経済および企業が抱える生産性の問題を解決するためには、個々の企業における
「イノべ-ション」が不可欠です。
企業にとっての「イノべ-ション」とは、「事業の創造」によって「付加価値」を増大させること
です。
また、それらを支えるために組織改革によって企業内の活性化を行うことも、「イノべーション」
といっていいでしょう。
企業はさまざまなリソースの集合体であり、外部環境との相互作用の中で「付加価値」を創出する
存在だと考えられています。
利益の源泉としてのリソースを発見し実現する主体は、企業にとっての主要なリソースのひとつで
ある「人」です。
そして、社会の変化や技術の進歩に加えて、そのような企業の主体的活動自体も、相互作用によって
企業にとっての外部環境を変化させていくのです。
こうしたダイナミックな動きの中で、持続的な競争優位を実現するためには、さらに「人」が重要に
なってくる。
特に、新たなポジショニング、新たなビジネスデザインを創造する人。
その人に機会を与え、力を発揮させ、育成する仕組みが大切になってくる。
人件費は、その「人」に対する分配であり、「人」にとってみれば自分へのリターンです。
それは、もちろん、労働市場の原理によって決定されるべきだと考えている。
しかし、人件費は企業が創出する価値の分配であり、単なるコストとしてとらえるべきものではない。
いたずらに、人件費を圧迫するような行動を誤って称賛しないためにも、また、価値創出において
無意味な分配論にとらわれないためにも、利益だけではなく、付加価値に着目すべきです。
□「付加価値」を創出する人と仕組み
そして、持続的な競争優位による付加価値の創出のために、「クリティカル・リソース」と「イノ
べ-ション・スパイラル」という考え方を提唱する。
「クリティカル・リソース」とは、企業の付加価値創出において、もっとも重要な役割を果たし、
それを調達できるかどうかが企業の成長を左右する経営資源のことです。
また、「イノべ-ション・スパイラル」とは、「つなぎ、試し、学ぶ」ことで、「クリティカル・
リソース」を活性化させ、増殖させる仕組みです。
「クリティカル・リソース」を可能にするのが、「イノべ-ション・リーダー」である。
新製品、新サービス、新市場を創造し、社会に新たな価値を提示し、高い付加価値率を実現する。
そして多数の「フォロワー」が参入し、キャッチアップしていく。
それによって「イノべ-ション」の成果は社会に広がり、「付加価値」額が増大する。
しかし、あまねく社会に広がっていくと、それは「イノべーション」ではなく 「常識」や「コモ
ディティ」になり、価格プレミアムが低下することで参入企業の付加価値率は低下していく。
こうした経済のダイナミズムの中で、米国は、ITや金融サービスにおいて多くのイノべ-ション・
リーダーを生んできました。
そうしたリーダー企業が自ら成長してきたことに加えて、周囲の企業にも波及効果を与え、連鎖的に
イノべ-ションを生み出した。
その背景には、米国の環境が世界中の「事業を創造する人々」を惹きつけてきたことがあり、それが
米国の富の源泉になっていました。
さらに、他国の企業のキャッチアップによって、IT産業、金融サービス産業における「イノべー
ション」の成果は、世界中に広まったのです。
新興産業国家の経済急成長によって世界経済は拡大しているが、それらの国の企業が、多くの産業に
参入し、フォロワー間の境争は厳しくなっている。
この状況の中で、日本経済の豊かさを維持するためには、より多くの日本企業が、いままで以上に、
イノべ-ション・リーダーとなることが必要です。
そのためには、日本の大企業を変えなければならない。
日本の優れた人材の多くは、依然として一部上場などの大企業に所属していることが多く、しかも
その優秀さが潜在化したままのことが多い。
日本でも米国のようなベンチャー型の事業創造を広げていくべきであるという意見は常にある。
しかし、現実の日本のベンチャー企業で成功しているもののほとんどが、米国のフォロワー型です。
ベンチャーによる事業創造が活性化しない原因として、日本の安定志向、失敗することを許容しない
文化、などが挙げられている。
□「事業を創造する力」の危機
バブル崩壊後、日本経済が低迷している間に、EUの経済成長、BRICsなどの新興産業国家の興隆、
天然資源の価格高騰による産出国への富の移転、などによって世界の経済地図は大きく塗り変わった。
そして、日本経済の相対的地位は低下した。
世界が日本を見る目、今では日本から見える景色が大きく変わってしまった。
資本は、金融資本市場の発達と自己増殖メカニズムによって、過剰に供給されるようになり、投資
機会を求めて世界中を飛び回っている。
また、新興産業国家の人々のスキルの向上により、企業が利用可能な労働力は大幅に増大した。
このように、資本も通常の労働も、大量供給されるグローバル経済の中にあって、「クリティカル・
リソース」とは何なのでしょうか。
それは、「事業を創造する人々」であると考える。
事業の創造とは、新事業の創造だけでなく、既存の事業を大きく変革すること(事業の再創造)
も含む。
いまや、資本や労働は、使ってくれる事業機会を求めているのです。
資本の力によって企業の経営権を取得しても、その事業を変革する人材がいなければ、成長はない。
そして結局は、そうした人材が企業経営に強い影響力を持つことになる。
繰り返しますが、過去、電機、工作機械、自動車産業などで、世界で成功してきた「日本企業」が、
いままで、日本での付加価値創出を重視し、日本での労働により多くを分配してきたのは、日本の
人材が「クリティカル・リソース」であったためです。
それが、日本に誇りと活力を与え、より多くの分配を得ることによる豊かさをもたらしてきたわけ
ですが、これは過去の経営環境の中の話である。
現在、企業の活動それ自体は、国家に制約を受けるものではない。
特に、企業を資本に対するリターンである利益の最大化を図る存在と見るのならば、国境など関係
ありません。
「日本企業」といえども、世界中でチャンスのある市場に進出し、もっとも最適な地域で事業に
必要な機能を展開し、それらの地域で付加価値を創出すればよいのです。
実際そうしてきたこの状態で、もし、日本の人材が「クリティカル・リソース」であり続けることが
できないのならば、日本での付加価値の創出と分配にとらわれることは、企業にとって足かせで
しかない。
企業は、成長・存続していくためには、日本での付加価値創出にはこだわらず、日本の人材への
分配も減少させるでしょう。
もし、グローバル経済全体の観点というものがあるとしたら、それでも何ら問題ない。
ただし、日本の豊かさは、もはや維持できない。
日本の誇りは、文化的な面もさることながら、経済成長によって豊かな社会をつくってきたことと、
一部の代表的な日本企業の世界市場での活躍によって支えられていたのではないでしょうか。
豊かさが失われてしまったとき、日本は世界に何を誇れるのだろう。
資本規制を復活させて、外資による日本企業の買収を防止しても、雇用規制によって、日本での
顧用を促進しても、この問題の解決にはならない。
逆に、グローバルな資本市場や労働市場とのリンクが絶たれることで、日本企業の競争条件が悪化
するだけである。
日本が、経済社会での誇りと豊かさを維持したいのならば、日本の中から、より多くの
「クリティカル・リソース」たる人材を輩出するしかない。
人材間の競争は激しくなっているが、世界経済の拡大によって全体のパイも大きくなっているのです。
力を発拝できるチャンスも拡大している。
現時点では、まだ多くの日本企業において、日本の人材のクリティカルさは失われていない。
いま、取り返しがつかなくなる前に、日本企業の経営者の方々にお願いしたいのは、自ら事業の
創造者でいていただきたいこと、そして、社内での創造への挑戦の機会を増やし、挑戦できるように
会社の仕組みを変えていただきたい、ということです。
ピーター・F・ドラッカーも、「監督者は制約と同居する。しかしリーダーは制約を除去する」と
述べている。
制約を除去して、「クリティカル・リソース」たる人材を増殖させていただきたい。
そして、より多くの日本の人材が、顔を上げて、目線を高く持ち、事業の創造に挑戦されることを
願っています。
協業のご案内
メルマガ登録(無料)はこちら
お問合せ・ご質問はこちら
ユニークセリングポイント(USP)
| 自社の本当の強み |
| ■自社の本当の強みとは ほとんどの社長は新規の見込み客などから、「御社の強みはどういった点です しかし、そこでの答えは「相手に自社と取引したいと思わせるにはどうすれば効果 もちろんアピール材料として「自社の強みの見せ方」も重要ですが、会社の長期 ここではこの自社の「強み」について掘り下げて考えてみましょう。 会社経営において、つねに自社の「強み」をいかした経営がなされているかどうか ここでいう「強み」とは、現在の自社のアピールポイントではありませんし、今期の もっとも重要なのは、 この部分さえしっかりしていれば、 と社長が自信をもって言い切れる自社の 「核」となる部分のことです。 しかしながら、そのような核を見極めることは容易ではありません。 また、後述するように核となる部分は社内外の環境によっても次第に変化してい 具体的に、自社の本当の強みについて以下のステップで確認してみます。
自社の強みについて考えるときには、できるだけ強みを特定して把握すること たとえばメーカーなどが「我が社の強みは技術力にある」とするときでも、どの 「ローコストで大量生産する技術力」と「高付加価値のオーダーメイドに応えて また、「自社の強みが商品開発力」にあると考える場合でも、「ユニークな商品 自社の強みを競合企業と比較するためには、さまざまな情報収集が必要にな 競合企業の製品やサービスを実際に利用したり、専門誌などによって業界動 多くの社長すでにこのような情報収集を行っていると思いますが、大切なのは たとえば競合企業が自社よりも優れた製品の販売を開始した場合、「その販 またどうしても自社の強みについては「過大評価」してしまいがちですので、時 厳しい経営環境をくぐり抜けて、会社がこれまで存続してきたのは、「過去」に しかし、これは将来に向けて会社存続を保証してくれるものではありません。 現在の自社の強みがそのままの形で5年後、10年後も通用するとは通常は これは特定分野における強みの「度合い」だけの問題ではありません。 たとえばAという精密機械製造のための熟練技術を「強み」として保有している それは世の中に圧倒的な「技術革新」が起こって、A製品がもつ欠点をすべて つまり既存の強みのレベルアップという「度合い」の問題だけではなく、既存と たとえば昔は音楽も映像も記録媒体としてはテープが使われていました。 この分野に関わるメーカーはテープ上にできるだけ高品質で記録するという目 しかし、ご存じのとおり、今ではデジタル技術の革新によって、音楽も映像も つまり「テープに高品質に記録できる度合い」はいくら高めても強みとはいえな また、最近では消費者の環境意識が高まるなか、自動車メーカーでは「低燃 自動車メーカーに製品を納入している中小企業にとっては、エコカーに対応し しかし、すでにハイブリット車の普及が加速しているように、近い将来には電気 その際には従来型の燃料自動車をエコ化する技術は、そのままでは電気自 つまりそれまで築き上げてきた燃料自動車製造における「強み」が通用しなく 自社の強みについて検討するためには、このような将来的な環境変化につい 既存の強みが急速に価値を失うこともある 自社の強みが明らかになったら、それらの強みを具体的にどのような手順で ここでは前述の「技術革新・ライフスタイルの転換点」なども意識した計画にす また、ここで重要になるのが「マイルストーン化」、「定量化」、「優先順位付け」 まずは「マイルストーン化」ですが、これは自社の強みを数年後までどのような たとえば自社の特定の製造技術を今後も強みとする場合、「1年後にはこのレ 次に「定量化」ですが、これは後の進捗管理の段階でどれだけ計画通りに進 たとえば、顧客サービスの充実を自社の強みとする場合、「3年後には地域で 「顧客満足度アンケートを3年後には10点満点申9.5点にする」など定量化す 最後に「優先順位付け」です。 前述のように自社の強みを高めていくためには、目前の競争に勝っていくため 問題はこれらのバランスです。 実際には現時点での自社の経営状況や現在の強みの発展性、次世代の強 特に経営状況が思わしくない場合には長期的な施策は後回しにせざるを得な 1.自社の価値はどのプロセスで生み出されているか 自社の強みをさらに明確化するために、ここでは自社の強みを棚卸しするた これは企業がその活動全体を通じて、どのような価値を生み出しているかを総 たとえば不況のなか、消費者の節約志向は高まるばかりですが、世の中には 普通のお店で売られているパンはせいぜい数百円程度ですから、このお店は おそらく特別な材料を使っているだろうことは容易に想像できます。 また、お客さんに自社のパンがいかに安全でおいしいかという告知活動も上 さまざまなプロセスで自社の強みをいかし、商品に価値を加えることでこのよう 価値連鎖の分析はこのような価値創出のプロセスをできるだけ分解して捉え この分析を行うことで、自社の経営活動全体のなかのどのプロセスで価値を これはその強みをいかに高めていくかということだけではなく、強みを利用して また、自社の価値連鎖を改めて見直した結果、現時点ではまったく価値を生 業種業態によって違いはありますが、会社経営における価値創出の流れ(価 たとえばある製造業者が前記の流れに沿って、価値連鎖分析を行ったところ、 ①購買物涜 入手困難な貴重な原材料を仕入れるルートを確立している 顧客ニーズを忠実に商品化するための設計ノウハウがある 共同物流によりコスト削減などの取り組みをしているが改善の余地あり 市場変化をタイムリーに把握する情報収集力がある 既存顧客へのフォローが不足しており、顧客流出比率が高い 社員の成長を加速する人材育成システム・評価システムがある このとき会社全体の価値を増大させる方向性としては、まず①②④⑥の強み この4つのなかで特にどれに注力していくかについては、それぞれの費用対効 そして③⑤のうち、たとえば⑤については緊急課題として改善に取り組むが、 このように自社の価値連鎖の分析ではそれぞれのステップごとの価値増大と 価値連鎖分析によって特に自社にとって強みと思われる部分を強化すること 川上から川下までをカバーする大企業においては、特定の機能を担う部門を 別会社化することで間接コスト負担が増すなどの問題点もありますが、中小企 たとえば外食事業者が自社の強みを考えるときにまず目が向くのは、「最終的 もちろんこれ自体は重要な要素ですが、もう少し上流にさかのぼれば、「購買 特に最近の消費者は、料理にどのような材料を使っているかということに非常 このように考えると外食事業そのものではなく、「購買物流」を自社の強みとし そのためには、「農協などの窓口との連携強化」、「契約栽培農家の直接開 さらに、多数の店舗を抱えるチェーン店では、店長やアルバイトをいかに短期 また、多数の店舗を効率的にコントロールするためのチェーンオペレーション これらの人材育成やオペレーションに関するノウハウを活用して、直接競合し 景気低迷で今後も不透明感が増すなかにおいては、自社の強みをしっかりと見 サクフリ株式会社のオウンドメディアで、「IT業界への架け橋になる」という |
ユニークセリングポイント(USP)
| サービス力 |
| ■サービスの重要性 重要となるのが、会社の独自性や差別化となる要因である。 製品やサービスを開発する場合には、その会社しかできない独自性を持つことが そうでなければ、資本力のある会社が、同じ製品をすぐに作り出して市場を制して 食品メーカーの競争などはその良い例でしょう。 その会社しかできない差別化要因をもつことで、競争力がつく。 また、差別化要因が会社の位置づけとして決定し、顧客への浸透が進む。 つまりブランド化である。 だから自社では、何を差別化要因とするのかを徹底的に考える必要がある。 マーケティングとは、差別化要因を見つけ、それを具現化する作業と言い換える 製品、サービスを独自化するには、コンセプトづくりが大事だ。 コンセプトをひと言で言えば、“ものごとを生みだすワンメッセージ”である。 すべてがこれに集約できる。 なぜなら、分かりやすくなければ伝わらず、さらにユニークでなければ多くの人は 評判にならないし、多くの社員を動かすこともできない。 例えば、今や工業製品や電化製品の分野などでは、どの会社でも技術力があ 自動車業界も見れば分かる通り、1社がある新車で大ヒットをとばせば、半年も経 すると、もはや自動車メーカーの競争力の源泉は、技術力ではなく、デザインで このような他社には真似が難しいソフト(アイデア)部分ならば、独自の差別化を コンセプトづくりのポイントは、3つのポイントを押さえて検討することにある。 1.ターゲット これは、購入するべき顧客層は誰かということです。 誰が購入すると最も高い価値を感じるかを考えてみよう。 マーケティングではベネフィットといっている。 これは、商品、サービスを得ることで、一番の利便性はどこにあるかを考える 購入する目的は、何らかの利便性を得るための消費活動であるので、それ しかし、ここで注意しなければならないのは、実用的な利便性よりも、その背 これは、アンケート調査結果なども参考にして、未来の種をつかもう。 これは、コンセプトは意外性が高くないと一般には浸透しない。 だから、多くの消費者が共感する、意外性のあるキーワードを導き出してみ このワードは、最終的にプロモーション展開をする時に参考となる。 コンセプトづくりは、製品開発やサービス開発の要である。 このコンセプトが明確になることで、マーケティングプロモーションやチャネル開発 例えば、広告コピーの考えの背景となるのが、このコンセプトになる。 また、重点的に強化するチャネルなども、このコンセプトが柱になっている。 だから、マーケティングでは、最初のコンセプトづくりが重要なポイントとなる。 パッケージとは、もともと梱包や包装することを言うが、ここでは、様々な技術、要 例えば、同じ技術であるならば、顧客は当然魅力的に映るほうの商品を選ぶ。 そこで様々な技術、サービスを集めて、このようにすれば活用できるということを これがライフスタイルの提案である。 例えば、米アップル社の「iPod」について考えてみましょう。 アップルのデジタル機器が入っている箱は、黒をベースに、製品写真、ロゴがシン 彼らは、箱まで含めて商品であると考えており、そこには当然友達にプレゼントす 商品を貰ったときに、思わず喜んでしまうという、サプライズまでを予想しているの また、iPodそのものが非常におしゃれである。 品質ももちろん大事だが、それ以上にデザイン性が問われる時代である。 黒と白を基調としたカラーリングは、他人に見せてもかっこいいと思わせる、感性 さらに、ライフスタイルの提案は、iPodだけの提案だけにとどまらない。 iPodに音楽データを転送するためのパソコン上で動くソフトウェア「i-Tune(s 音 企業が顧客に商品やサービスを提供する形には、分類のしかたにより様々な分 1.部品や素材で提供するパーツ型 2.ソリューションで提供する 3.パッケージで提供する このようにモノを提供する場合、3つの型のどれか、あるいは複合して提供するこ 最近は、パッケージ型の優位性が年々高まっている。 なぜなら、私たちの生活を彩るためには、1つの製品、1つの商品だけでは不十 商品やサービスの提供方法に3つの型があることを提示したが、結局デジタル 付加価値とは、希少性であったり、差異性であり、期待性のことである。 この人しかできない、この会社しかできないという希少性。 そして、この製品はほかと違うという差異性。 また、この製品を触るとワクワクする、成長していることが分かるなどの期待性で この3つの価値観が付加価値となって伝わったからヒットしたのである。 あなたの会社でも、「パッケージ」を念頭に置きながら、付加価値を高めた製品、 |
ユニークセリングポイント(USP)
| USP(ユニークセリングポイント)とは? |
|
営業会社にとって、競合他社との違いを明確にしていかなければ埋没してしまいます。 その解決策が他にない独自の売りとなるユニークセリングポイント(USP)の構築です。 商売を成功させるための最大の秘訣は、よそにはない「売り」があること、よそとは 商品でもサービスでも、よそにはないものを提供しなくてはならない。 ほとんどの営業会社はただ漫然と、よそと同じようなものを、特に顧客からは同じとしか 大きな利益をあげようと思うなら、何とかして、よそと違う「売り」を作ることです。 どこにでもある、すぐ手に入るようなものではだめ。 ありふれたものを作っていては、よそとの違いは出せないからです。 会社を立ち上げ、運営し、維持発展させる、そのあらゆる段階で、よそにない「売り」 しかも単に違うというだけでなく、その違いを理解し評価してくれる大きなマーケッ お客様(見込み客)にとってあなたの専門性は当然と思っており、 専門的サービスを提供する事業者の多くは、顧客は自らの専門性を買ってくれていると 対応がスムースに問題なく解決しても、それが本当に優れたものかどうか彼らにはわから しかし、対応にあたりあなたからの定期の経過報告の有無により、 あなたが売っているのは扱い商品・サービスではなく、むしろ人間関係なのです。 組織人として、会社の代表であるという意識で臨んでいるでしょうか。 組織人としての基本動作こそUSPとして武器になるのです。 人が商品やサービスを購入するのは理屈や理論ではなく 感情であると言われています。 商品・サービスを購入しようと考えたとき、人はその商品を使ったことがないので、その それなのに商品・サービスを購入するのは「その商品が良さそうだから買う」のです。 そして、営業マンの好感のもてる態度に購入を決めたりもするのです。 人は「よさそうに見える」、「好感のもてる」といった見た目で判断(感情)しているこ お客様はあなたの商品・サービスを買うのではなく、商品がもたらす利益(メリット)を そして多くの場合、この点(USP)にこそ最も注カすべきなのです。 価格を売りにするのではなく、「こんな品質とサービスが受けられますよ」と、顧客を それも価格を告げる前に、です。 この考え方は、あなたの市場が厳しく競争の激しいものであれば、よけいに重要に 自社(店)の「売り」が見つからなかったり、「売り」はあっても今のままではそれを伝 価値を付け加えるとは、顧客に何かプラスアルファのものを提供するということです。 何かよそにはないもの、顧客がまったく予測していないものです。 それを受け取ることで、その分まで喜んでお金を払う気になってもらうためのものなの 付加価値をつけるからこそ競争相手と差がつき、顧客は、価格が高くても「買って良かっ 絶好のタイミングで新しいコンセプトを見つけ出してそれを製品化し、商品として 事業を成功させるためには、市場の教育は常に必要だ。 しかし、市場に新しいコンセプトを一から教えるのと、お客様にあなたの商品の「売り」 つまり、なぜ取引の相手としてあなたなり、あなたの会社なりを選ぶかという、確固 この重要な教育ツールがUSPです。 ただし、そのためのコストが高くなってはいけない。 何か新しいものを売り出そうと思ったら、商品の選択は慎重にしましょう。 あなたにとっては新しくてわくわくするような商品かもしれないが、だからといって 必ずしも売れるということにはならないからです。 このリスクは大きい。 いちばん大切なことは、マーケティングは自分の商品やサービスにではなく、顧客 顧客が求めるのは、自分たちのニーズに応えてくれるものであって、あなたのニー これがマーケティングのすべて。 常に顧客の立場に立ち、いつでもそのニーズを満足させられるようにしておくこと。 会社経営とはそういうものだ。 強力で説得力のあるUSPを作り、その約束をしっかり守るようにしていけば、すぐ に希望する水準の価格をつけられるようになります。 もちろん一部には離れていく顧客、あなたの会社とはもう取引をしないという顧客 しかし、それで構わないのです。 顧客によってはこちらの利益にならないところもあるのです。 そのようなところには、よそへ流れていってもらえばいい。 利益にならないところを相手に無理してサービスを続けても、あなたにとってのメリ 値段だけでものを買うという顧客はほとんどいません。 「安物買い」の顧客にしても、安い買い物がいい買い物とは限らないことに気づき 顧客が探しているのは「最も価値あるもの」なのです。 常にしたがうべき基本法則は、「価値あるもの」です。 そして、USPを作ることで余分な費用はほとんどかかりません。 あなた(会社)が見込み客と出会うあらゆる接点を洗い直しましょう。 出会いは受付窓口、名刺、会社のビルや店舗やオフィス、パンフレット、会合、営業の 出会いの瞬間を1つでもないがしろにしてはなりません。 それが唯一のチャンスかもしれないからです。 多くのお客様(見込み客)がサービス業の会社を選択するとき、彼らはその会社の サービス業にとって重要なのは人間関係であり、その前提となるのが「見た目」であり、 人間の五感は視覚と聴覚で93%を占め、言葉(文字)だけでは、7%しか相手には伝 言葉7%(言葉そのものの意味や話の内容) 声38%(声の大きさや高さ、強弱、話すスピード、イントネーション) 外見55%(表情、動作、立ち振る舞い、しぐさ、服装) 人は相手の考えや意見を聞くとき、無意識に外見から受ける第一印象に基づいて、話 営業の立場からすると、まず外見で相手に良い印象を与えれば、相手は話の内容に 第一印象ほど怖いものはないのです。
・あなたは見込み客の心に自分を位置づけ ・そのポジショニングは「他にない」一つの単 ・そのポジショニングは競合に対して差別化 その利点を強調することです。 フットワークの軽さや、個々の仕事への目配りの良さ、などを。
サービス業において、多くの場合顧客がサービスを必要とするのにワクワクするようなこ 家屋の破損、歯痛、自社(店)で雇う税理士(会計士)、万一に備えるための保険など。 治療で歯の痛みが治っても、事故を起こし、満足の行く対応であっても、一度満足してし 大切な保険証書はファイルに綴じ込まれたままで何をしてくれるわけでもありません。 あなたは「存在感を示し続けること」で顧客満足を獲得していくべきです。 あなたが顧客に提供して喜んでもらったサービスを思い出させ、あなたがまだ頼りにでき あなた(会社)が記事になったこと、マスコミに報道されたこと、良いニュースはどんな ファックス、ニュースレター、ハガキ、お客様の声 等々。 お客様の目に入らなければ、あなたは存在しないも同然なのです。 上記のことを継続実行することが、あなたのユニークセリングポイント(USP)となるの 顧客ニーズが多様化・複雑化している現在、販売の土俵を決めて戦力を集中しなければ 万人を対象に、あなたの扱う商品・サービスを販売すべきではありません。 その商品・サービスを、どのような相手に、どのように販売するか、明確に設定すること ポジショニングを明確にしなければ、自分がどこで誰を相手に勝負しているかもわか ポジションを決め、ターゲットを明確に定め、そのターゲットに向けてもっとも効果の高 ポジションを明確に設定しないと成功の確率がなかなか上がりません。 あなたのポジション、マーケットを明確にせず営業を推進していくことは、“下手な鉄砲 あなたの土俵設定(セグメンテーション:マーケットを細分化)の基本は、あなたの商品 訳すと、「競合他社にない独自のウリ・強み」です。 営業会社にとって他との違いを明確にしていかなければ埋没してしまいます。 他の会社には提供できない、あなたならではの商品やサービスとはいったい何ですか? これを短い言葉でわかりやすく表現したものが、USPです。 競争相手が多ければ多いほど(つまり、あなたがその他大勢の一員であればある 「30分以内でお届けできなったときには代金はいただきません!」 まだ宅配ピザというものが浸透していない時に、このUSPはものすごい短期間に宅配 宅配にありがちな「遅いのではないか?」「届く頃には冷めててまずいのではないか?」 また、ある仕出し弁当屋がありました。 味は大して美味しくありません。当然、売れませんでした。 しかし味も何も一切変えずに、「葬儀専門の仕出し弁当屋」にしただけで、売上が急速に ただ「弁当を頼む」のではなく、「葬儀の時に弁当を頼む」と言った方が、よほど具体的 “自分のための”商品を探しているのです。 「これは、あなたのための商品です。」と言ってくれる人を待っているのです。 すると、あなたはもう一歩進めて、さらに新しい付加価値を顧客に提示して、買ってもら それをいつも、よそよりも速く、安価に、上手くできて、手軽で、信用がおけて、誠実な 顧客の本当のニーズや望みがどこにあって、どんな問題を抱えていて、どうしたら解決を そうすれば必ず売れるのです。 ただし、商品ありきではありません。 問題解決業であるあなたが商品を売るのは後です。 お客様の抱える問題の解決の手段として、あなたの商品・サービスがあるのです。 言い換えるなら、あなたは自分で思っている以上にありふれているということです。 お客様の目から見て、まったくありふれたものであるなら、あなたの望むような結果には お客様の立場から言えば、似たり寄ったりなら、あえてあなたに替えるといったリスクを そのためには、自分に問いかけてみてください。「なぜ同業他社ではなくうちから買って これこそは、事業を成功させる秘訣なのです。 そして、一部の同業他社がとてつもなく大きく増収している最大の理由でもあります。 彼らは、よそとの違いが利益を生み出すということを知っているのです。 独自のUSPを開発するためには、違いを出すために自分に何ができるのか、何を変え 話せば教えてくれるはずです。 それも無料で。 出向いていって尋ねてみましょう。 あなたの会社(店)や商品や業界そのものについて、どのような不安、不満、望み、 それも必ず顔を合わせて、可能な限り自分で直接尋ねてみることです。 しかし、たとえ難しくても探し続けなければいけないのです。 よそとは違った、独自性のある存在でなくてはなりません。 1.広い選択肢 2.大幅なディスカウント 3.的確なアドバイスや補助 4.利便性(ロケーション、豊富な在庫、配達の 5.最高級の製品(サービス) 6.迅速なサービス 7.特別な各種サービス 8.長期的な保証、または広範囲にわたる保証 9.その他、ライバルには提供できない特別な点、 換言すればお客の購入理由です。 このニーズ(直接購入理由)とその他の環境、気分など(間接購入理由)が合致したとき 従ってセールスマンがお客の前でセリングポイントを話すということはお客が買って
■セリングポイントづくりの手順 1) 当該商品及びサービスに関する調査分析 (1)アンケート、インタビューあるいは営業同行を通じて、商品及びサービスに (1)調査、分析で作成した表を基に、実際の営業活動で顧客のニーズに合わせ そのためには商品の特徴がいかなる理由で、相手の利益に結びつくかを明 FABシート(製品、椅子のFABシート)は、この点ですぐれた手法です。 ① 骨組がスチール製ですので丈夫になっております。つまり長もちして経済 ② 背もたれが傾斜していますので楽に坐れます。つまり、長時間の会議・研 ③ 坐部が布張りです。ということは、坐り心地がよく、長時間の会議に適して ④ クッションが入っており、疲れがありませんので、会議・研修に集中できる ⑤ 茶色ということは、床や壁の色調にマッチして部屋のイメージアップに貢 ⑥ 足の先端にすべり止めがついていますので、床に傷をつけません。つま
<利益(メリット)の代表的なもの> キーワード ・・・・・・ SPACE S=Safety(安心、安全、安定) P=Performance(品質、機能、効果) A=Appearance(外観、イメージ) C=Comfort(気分、安楽、快楽) E=Economy(経済性、金銭の節約) 従って、お客の利益は何かということを的確に把握して、利益主張をしなければなら 製品やサービスを提供することによりお客がどんな問題や悩みが解決できるか、 ① 金銭・時間が節約できる ② 利益倍増に貢献する ③ (会社の)イメージアップに役立つ ④ 感じよく働ける ⑤ 仕事の達成度が多くなる ⑥ 効率がよくなり、お店が繁盛する ⑦ 省力化ができる(人手を少なくできる) ⑧ 作業工程の合理化ができる ⑨ 生産性の向上に貢献する ⑩ 作業改善につながる ⑪ コストダウンできる ⑫ 事務の効率化を通じ会社・従業員のプラスになる ⑬ 競合他社との差別化ができる ⑭ 業界での主導権をとる ⑮ 担当者の個人的満足(ES)を満たせる ⑯ ゆき届いた技術とアフターサービスができる ⑰ 簡単な使用法である ⑱ 不良品の削減ができる ⑲ 信用が増大する ⑳ 従業員によろこばれる ぜひ早急にあなたのUSPを考えてみてください。 出来上がったUSPがあなた(会社)のスローガンとなり、競合他社との差別化策となり お問合せ・ご質問はこちら
|
お問合せ・ご相談はこちら
企業運営に欠かせないマーケティング、業務改善、リスクマネジメントの3つの仕組みづくりを
倒産に見舞われています。「知っていれば」「対策を講じていれば」倒産を防げたはずの企業が多く存在する
ことを、私たちは数多く見聞きしています。
事業運営に欠かせないマーケティング、業務改善、リスクマネジメントの分野で全力を尽くして支援して
まいります。
| 対応エリア | 静岡・愛知県内、東京周辺 |
|---|